日本美術を海外に広めた林忠正さん。でも、なぜか「国賊」とまで呼ばれたという話、気になりませんか?番組だけでは拾いきれない背景を、わかりやすく整理してみました。
【放送予定ご案内】
高岡出身の世界的美術商で民間人初の万博事務官長・林 忠正のNHK3連チャンの3回目です。
〇NHK Eテレ『先人たちの底力 知恵泉(ちえいず)』「不屈の美術商 林忠正 “国賊”と呼ばれて」2025年5月13日(火)22:00〜22:45https://t.co/BvhM6YRD3x— 高岡市立博物館 (@takaoka_mm) May 5, 2025
NHK「知恵泉」で取り上げられる林忠正さんは、日本の美術を海外へ紹介した立役者。でも当時の日本では「文化を売った」と見る声もあり、功績の裏で非難も受けていました。番組ではその功績が主に描かれるでしょうが、「どうして国賊と呼ばれるまでになったの?」という声が視聴者から上がりそうです。この記事では、そんな素朴な疑問に答えるかたちで、林忠正さんの人生と評価の流れをやさしく紐解いていきます。
林忠正 海外に流出させた作品とは
パリ万博で売られた浮世絵の数々
林忠正さんが注目されたのは、1878年のパリ万国博覧会をきっかけに始めた日本美術の取引。特に浮世絵や屏風など、当時の日本では見向きもされなかった品々を海外に届けました。西洋の芸術家たちはその魅力に目を見張り、ここからジャポニスムというブームが始まります。
t.cohttps://t.co/XALzVjcyNh— 鈴木五郎 (@Bonze_Yakuside) April 28, 2025
- 影響を受けたのはゴッホやモネなど、名だたる画家たち。
- もしも林忠正さんがいなかったら、これらの作品は焼却されていた可能性も。
流出=文化損失と捉える声も
ただし、これが国内で問題視されたんです。「自国の宝を売った」という見方が生まれ、やがて「売国奴」「国賊」という言葉が飛び交うように。当時の日本では浮世絵は“紙屑”とまで言われていましたから、評価のギャップが生んだ批判ともいえます。
企画展「知られざる至極の木版画 摺物」開催中!
こちらは、北斎の弟子の魚屋北渓の摺物。能の演目「白鬚」を描いています。舞を舞う白鬚明神の衣装など細部までよく描きこまれています。少し角度を変えると金銀摺りがキラリ✨。署名の下にはパリで活躍した美術商・林忠正の印が捺されています。 pic.twitter.com/2qToa8bB0l— 北斎館 (@hokusai_kan) September 21, 2023
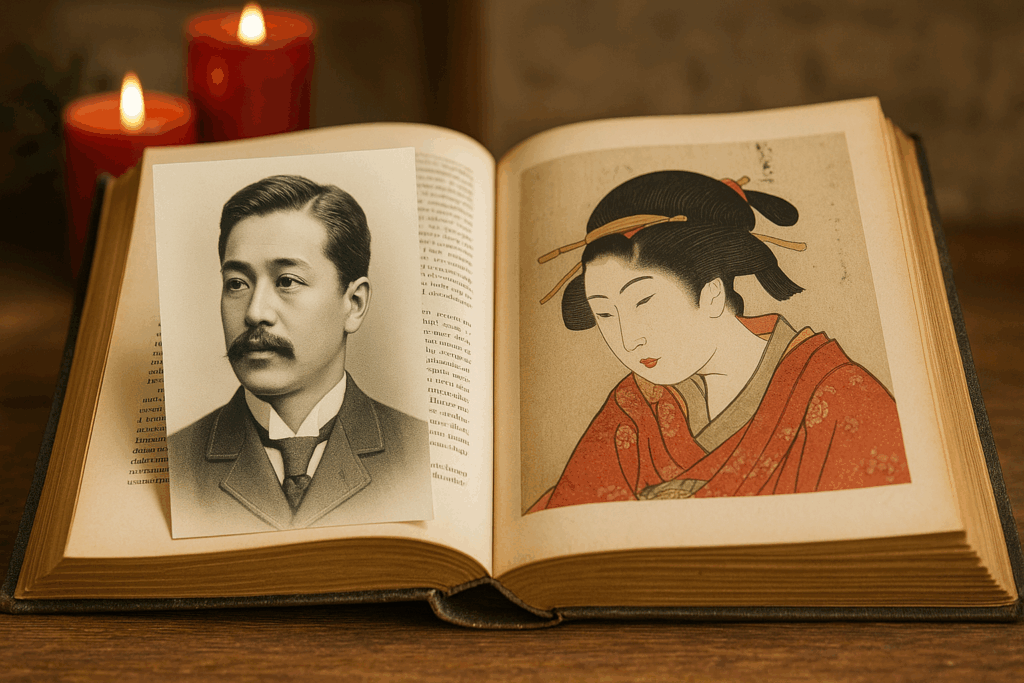
「そんなにまで言われていたなんて…」と驚いた方も多いのでは?
背景には、美術に対する無理解や、成功者へのやっかみも見え隠れします。
林忠正 美術商なのに国賊と言われた訳
社会的バッシングと誤解の連鎖
1900年のパリ万博で事務官長を務めていた林忠正さん。その頃、ある社会主義者の転落死事件があり、なぜか林忠正さんが疑われ、「殺し屋を雇った」とまで書き立てられました。まったく根拠のない話だったのですが、当時のメディアは面白おかしく報じてしまったんですね。
のちにこれは「失恋による自殺」と明らかになりましたが、林忠正さんのイメージは傷ついたままでした。
本日のNHK #歴史探偵 は「万博と日本」。まずは、1900年パリ万博から。事務官長の林忠正が登場! pic.twitter.com/lvSraXISoC
— 藤原書店 Fujiwara-shoten (@FujiwaraRSS) April 16, 2025
晩年の困窮と名誉回復の道
その後、林忠正さんは美術商を辞め、弟を亡くし、報酬もないまま帰国。日本での生活は決して順風満帆とは言えず、困窮の中でこの世を去ります。しかも、亡くなった後も「国賊」として扱われ続けたのです。
ですが、1980年代になって事態が変わります。孫の嫁である木々康子さんが奔走し、林忠正さんの功績がようやく認められ、「日本美術界の救世主」と呼ばれるようになったのです。
まさに、時代の価値観が大きく変わっていった結果でもありますね。
左下にいかにも元からあるような感じで林忠正の丸印があります。この摺物も林によってヨーロッパに渡ったのでしょうね。 https://t.co/9SXXVLvotQ
— 二楽山人 (@hitomaroeiku) August 16, 2024
まとめ
林忠正さんが「国賊」と呼ばれた裏には、価値観の違い、嫉妬、誤解といったさまざまな要因が重なっていました。今ではその功績が広く評価されていますが、当時はとても厳しい風当たりだったのです。番組を観て気になった方にこそ、知っておいてほしい背景です。
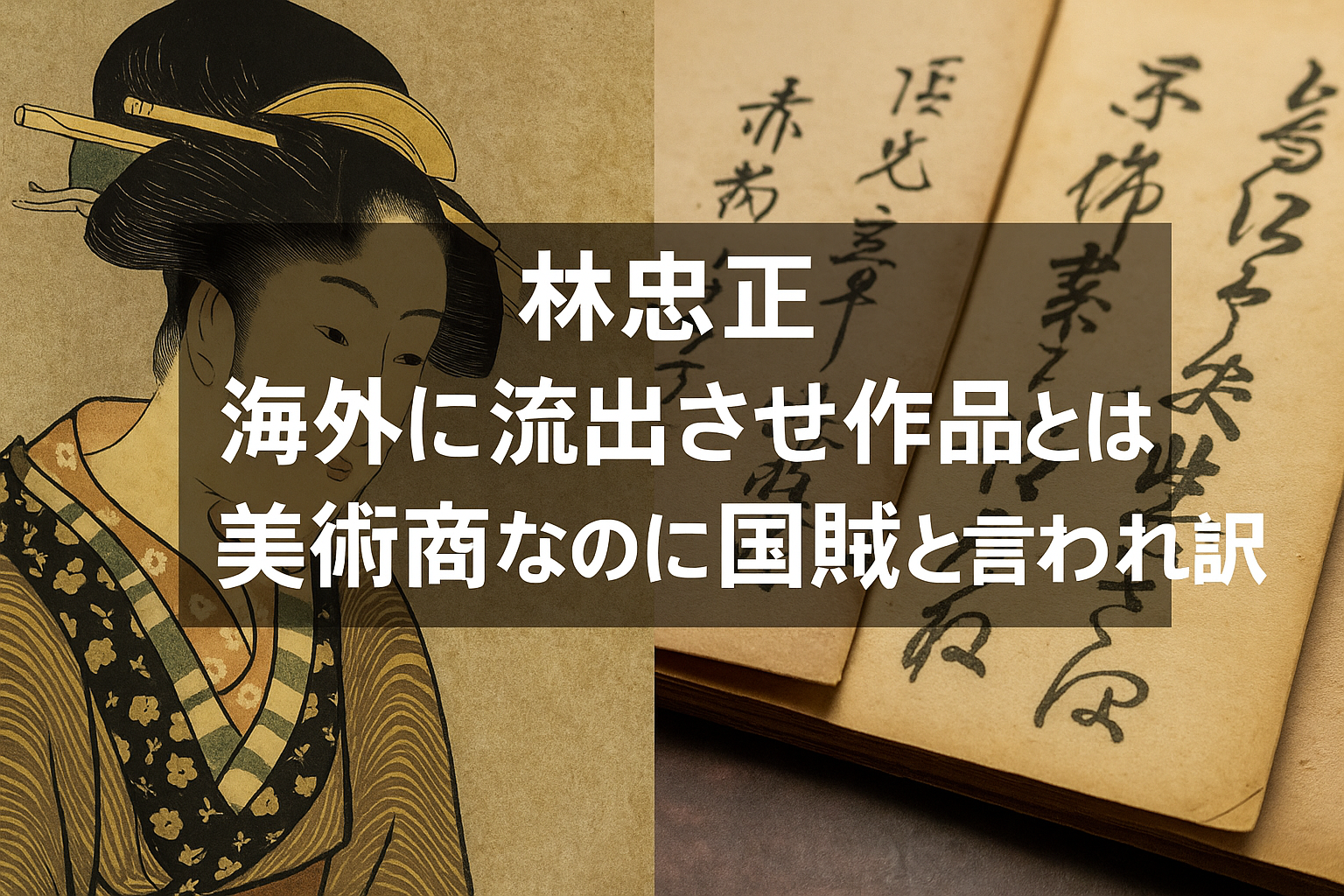
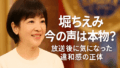
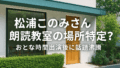
コメント