「水戸黄門といえば印籠」。そんなイメージにふと引っかかりを感じた方もいるのでは?NHK『偉人の年収 How much?』で紹介された徳川光圀の“印籠じゃなかった理由”と“自筆の正体”に、静かに注目が集まっています。
2024年5月放送予定の『偉人の年収 How much?』では、水戸藩主・徳川光圀の収入を手がかりに、その人柄や生き方にスポットが当てられます。
中でも反響がありそうなのが「印籠ではなかった」という事実と、番組内に登場する“自筆の品”。「あの場面、結局何だったの?」とモヤモヤを感じた視聴者に向けて、今回はそのヒントを探っていきます。
徳川光圀 印籠じゃなかった理由
なぜ「印籠=水戸黄門」は後年の創作なのか
テレビ時代劇ではおなじみの“葵の御紋の印籠”ですが、実は徳川光圀がそれを使って旅をしていたという史実は見当たりません。

実際の光圀さんは全国を巡ることなく、水戸藩内での政治や学問に力を注いでいた人物です。
つまり、「印籠」はあくまで後世の演出。定着したイメージと史実の間に、ちょっとした“ズレ”があったということなんですね。
実際に持っていたのは「知」と「誠意」のしるし?
番組で登場した「自筆の何か」に注目が集まりましたが、これが何かを明確に語られる場面は少ないかもしれません。
有力なのは、徳川光圀がしたためた書状や漢詩など。
それらはおそらく、訪問先への礼状や自己紹介を兼ねた“挨拶代わり”のようなもので、威厳を示す道具ではなく、人柄や教養を伝える静かな存在だったのではないかと考えられています。
徳川光圀 番組で見せた自筆の正体
番組で映った“自筆の品”、実は何だった?
『偉人の年収 How much?』の放送では、徳川光圀の自筆とされる書が登場するシーンがありそうです。
でも、それがどういう文面だったのか、あるいは何の目的だったのかは番組では深く語られない可能性もあります。
「で、あれって結局なんだったの?」と思った方は、私だけではないはずです。
自筆の書が光圀さんの“本質”を映している?
印籠が“権威の象徴”だったとすれば、自筆の書は知性と誠意の象徴とも言えそうです。
特に徳川光圀は『大日本史』の編纂に心血を注いだことで知られ、その思考や理想を文字で残すことに重きを置いていました。
番組の演出がその一面を拾っているとすれば、単なる史実紹介ではなく、光圀という人物の本質に一歩近づけるヒントになるのではないでしょうか。
【まとめ】
『偉人の年収 How much?』は、時代劇では語られなかった徳川光圀の“もうひとつの姿”を垣間見るチャンスです。
印籠ではなく自筆の書という切り口から、視聴者のイメージがじわりと塗り替わる──そんな番組になるかもしれません。
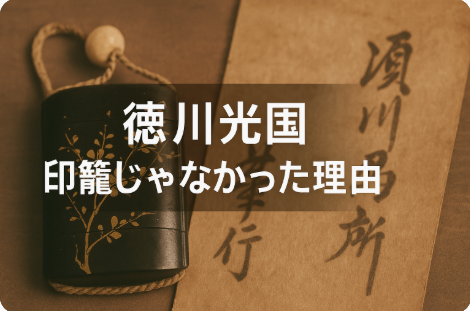
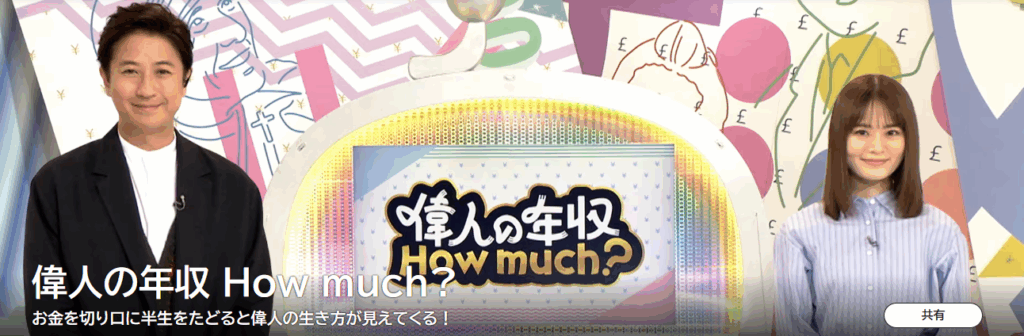
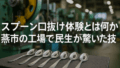
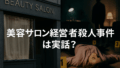
コメント