ノルウェーで寿司といえばサーモン。でも「どうして他のネタがないの?」と思った方も多いかもしれません。今回紹介するのは、そんな疑問に挑んだ日本人寿司職人のリアルな物語です。
出典:https://www.tv-tokyo.co.jp/japan_suitcase/?cx_search=program&
『JAPANをスーツケースにつめ込んで!』で取り上げられたのは、寿司といえばサーモンが定番のノルウェー。この“偏り”に風穴を開けようと立ち上がった日本の寿司職人たちの姿が印象的でした。番組を見て「なんでサーモンだけ?」「他の魚も食べられるのでは?」と感じた方へ。背景にある歴史、文化、現地事情をやさしく掘り下げてみました。
ノルウェーとは?寿司との意外な関係性
サーモン寿司普及の裏にあった国家戦略
1980年代、ノルウェー政府が余剰サーモンの新たな販路として打ち出したのが「プロジェクトジャパン」。当時、日本ではサケの生食文化が定着しておらず、その隙を突く形でノルウェー産養殖サーモンが寿司ネタとして売り込まれました。実際、首相自ら来日してのプロモーションもあったほどです。
人気のノルウェーサーモンは円安で国内の養殖サーモンと価格の逆転現象も起きていたので為替の影響を受けにくく、安定供給が可能な陸上養殖は特に飲食業の仕入れ先として需要ありそう
円高になると苦しそうではあるが
丸紅など4商社、陸上養殖サーモン大量出荷へ https://t.co/PdTmND883L
— こいけ@コツコツ投資 (@Soko2Investor) October 23, 2024
なぜノルウェーではサーモン一強に?
品質管理の徹底や安定した流通体制、クセのない味が支持され、サーモンが圧倒的な地位を築きました。現地では「生魚=サーモン」というイメージが根強く、他の魚が広がりづらい背景があります。
なぜサーモン一強?寿司ネタの偏りとその背景
多様なネタが普及しない背景
マグロやイカ、エビといった寿司ネタは日本では定番でも、ノルウェーではあまり浸透していません。というのも、現地では燻製や加熱が基本。生食文化が薄いため、受け入れのハードルが高いのです。
現地の流通と安全性のバランス
サーモンの養殖技術は他魚種に比べて飛び抜けており、寄生虫リスクの低さも評価されています。また、仕入れや価格面の安定も魅力で、結果的に「サーモンだけで十分」という構図が生まれているのです。
今日は #国際寿司の日!🍣
知ってた?💡
サーモン寿司は外交戦略で生まれたんだよ~⁉️
1980年代、ノルウェー政府が「生で食べられる養殖サーモン」を日本に売り込み、
当時は「生の鮭?無理😥」と寿司業界に拒否されるも、
今ではサーモンが回転寿司の王者に!👑#企業公式相互フォロー pic.twitter.com/7y3k3fdhI9— 【公式】くまポンbyGMO (@kumapon_jp) June 18, 2025
日本人職人の挑戦とJAPANスーツケース旅の意義
サーモン以外を伝える工夫とは?
佐藤健一さんや中村陽子さんといった寿司職人が現地で提供したのは、マグロや白身魚、ホタテなど日本らしいネタを活かした創作寿司。ノルウェー産の白身魚を“鯛風”にアレンジした握りや、ポン酢やゆず胡椒といった調味料で味のバリエーションを加えるなど、細やかな工夫が随所にありました。
寿司を通じた文化体験の提供
会場ではマグロの解体ショーや寿司握り体験も実施され、食を通じた文化交流が進んでいました。「初めて自分で握った寿司が思ったより美味しかった」という声もあり、体験としての寿司が受け入れられつつあることを感じました。
会社のイベントでマグロ解体ショーnow pic.twitter.com/qMqoxliYxL
— りゅう君 (@Ryuukunn24) July 5, 2025
ノルウェー寿司と日本文化のギャップ
食文化と価値観の違いがもたらす戸惑い
「いただきます」や「ごちそうさま」が日常にないノルウェーでは、食事に対する“感謝”という感覚が新鮮に映るようです。また、懐石料理のような一皿ずつの展開も「何品来るの?」と驚かれる場面があったそう。
がんこさん 懐石料理 いいね pic.twitter.com/BrsYDqgmX0
— すっさん (@kazu19734826) June 24, 2025
箸やサービスに対する驚きのリアクション
お箸の扱いに苦戦する姿もありましたが、それもまた楽しみの一つ。ある来場者は「箸は難しいけど、ゲーム感覚で面白かった」と笑っていました。こうした“文化の違い”が、逆に親しみの入口になるのかもしれません。
■ まとめ
ノルウェーで寿司=サーモンという構図ができた背景には、歴史や技術、文化の違いなど様々な事情があります。
そんな中、日本の寿司職人たちは丁寧に、しかし確実に“寿司の多様性”を伝えようとしています。たとえば、マグロや白身魚をうまく現地仕様にアレンジした工夫は、寿司文化の幅広さを感じさせてくれました。
次に寿司を食べるとき、いつもと違うネタを試してみるのも面白いかもしれません。



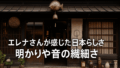
コメント