「円の一周が360度」って、誰がどう決めたんだろう?子どものころから当たり前に覚えてきたけど、あらためて聞かれると意外と答えに困る…。そんなモヤモヤを**チコちゃんに叱られる!**で今回スッキリさせてくれそうです。
円360度なぜ古代バビロニアで決まった?という素朴な疑問。実はこの「360」という数字、古代バビロニアの60進法や天文学と深く結びついていたんです。数字の扱いやすさや暦の仕組みまで絡み合って、ただの偶然では済まされない歴史があることに気づくと、学校でなんとなく覚えたこの単位が急に面白く見えてきます。チコちゃんで気づく謎の起源を一緒にたどってみましょう。
円360度なぜ古代バビロニアで決まった?
太陽と一年を360で区切った知恵
太陽の動きをもとに1年を約360日と捉えていた古代バビロニア人。当時の人々は60進法を使っていて、60や360という数字は生活に根付いていたそうです。
しかも360は24個以上の約数を持つ、いわば“割りやすいスーパーナンバー”。角度を分けたり測ったりするのにもってこいの数だったというわけです。
クレイタブレットに刻まれた天文学
クレイタブレット(粘土板)には、当時の天体観測記録や黄道を360分割した図などが見つかっているそうです。
信仰と観測のどちらにも役立った数字だったということですね。ちなみにこの頃、他の地域ではまだ度数法が発達しておらず、バビロニアの先進性がうかがえます。
教科書にあった粘土板は英語だとクレイ・タブレットなんやぁ。しかも書いてる内容がお店へのクレームて、4000年経っても素材が違うだけでやってる事あんまり変わらんのな(丁度近所のスーパーのお客様の声に1件入れたとこ)。 https://t.co/kllCL5hP3Q
— 那由他の星ははいいろ (@nayuta_stars) May 23, 2023
チコちゃんで気づく謎の起源
100度じゃダメなの?
今回の**チコちゃんに叱られる!**でチコちゃんが「100度じゃダメなの?」と問いかけた場面、妙に印象に残った方も多いのでは?
伊集院光さんや池田エライザさんも、「たしかに…」と苦笑しつつ耳を傾けていました。たしかに「100」や「400」って見た目は区切りがよさそうですが、360度には“扱いやすさ”という大きなアドバンテージがあるんです。
他文明でも? 比較の面白さ
たとえば古代ギリシャのヒッパルコスも星の位置を360度で表していた記録があり、さらには中国の一部地域でも独自に似た単位があったとの話も。文化が違っても「この数は便利!」と気づいたのは興味深い一致です。
最近ではNASAも360度全天球カメラを使って宇宙観測に活用していて、意外と現代でも活躍中なんです。
長野県松本市の国宝・松本城は天守と水堀が近いため、ほかのお城にない写真表現が楽しめる。
名付けて「水玉城」
撮り方は簡単。全天球(360度)カメラを長い一脚に取り付け撮影するだけ。リトルプラネット効果で透明感のある水晶玉に浮かんだカッコいいお城が撮れる。#長野県 #松本市 #松本城 pic.twitter.com/B3038zLWTN
— 林 貴(月見烏) (@rinki0601) July 20, 2024
日常にあふれる「360」と「60」
こんな場面でも使ってる
・時計の60分、1時間 ・方位磁針の360度 ・地球の経度・緯度 ・ゲームコントローラーの「360°ビュー」 ・料理レシピのオーブン温度設定
ちょっと意識してみると、身の回りに「360」や「60」が思ったより多く潜んでいるのに気づきます。
教育現場でも役立つ?
小学校で「円は360度」って教わって、「なんで100度じゃないの?」と思った記憶がある人、けっこういそうですよね。今、大人になってからこのテーマにふれると、「なるほど、そうだったのか」と思わず誰かに教えたくなる瞬間が生まれるかもしれません。
実生活への活用アイデア
・子どもに**「割り切れる数の便利さ」を伝える話題として ・時計や地図を使った家庭内ミニクイズ**にしてみる ・学校の自由研究で「角度の起源」をテーマにするのもおすすめ
【まとめ】
「円360度なぜ古代バビロニアで決まった?」という疑問、あらためて深掘りしてみると、60進法、天文学、暦など多くの要素が絡んでいて、じつはとても合理的な選択だったのかもしれませんね。今回の**チコちゃんに叱られる!**をきっかけに、「数字の意味って奥深いな」と感じた方も多いのでは?
歴史をたどるうちに、普段使っている360度や60分が、思っていた以上にすごい発明だったことに気づけたのではないでしょうか。こんな風に日常の“当たり前”をちょっとひっくり返すと、知識って自然と頭に入ってきますよね。


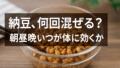
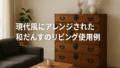
コメント