青森ねぶた祭といえば、迫力満点の武者絵が浮かぶ人が多いですよね。でも今年の放送でちょっと気になったのが「鼻」。なんだかやけに目立ってた…そんな風に感じた方、実は少なくないんじゃないでしょうか?
ねぶた祭といえば、目力や衣装の鮮やかさが印象に残りますが、**「鼻」**の造形にスポットが当たることは珍しいですよね。今回の特番では、王林(おうりん)さんがガイド役として、あえてその“鼻”に注目。なぜ鼻がそんなに強調されるのか…その裏には、歴史や風習、職人の思いが込められていました。普段は見逃しがちなこの部分、実は深い意味があることに気づかされます。テレビを観て「えっ?」と引っかかったあの瞬間、もう一歩深掘りしてみませんか?
ねぶた 鼻の秘密に込められた意味とは?
王林さんが伝えた“鼻のこだわり”
特番で王林さんが語った「鼻」には、表現力や魂の込め方が詰まっていました。実際のねぶた制作では、顔全体のバランスよりも鼻の立体感や陰影に力を入れるという職人もいるそうです。鼻は見る角度によって表情が変わるため、見る人の印象を左右する大切なパーツなのだとか。
t.cohttps://t.co/dN3pMhNlYJ— 写真家 加藤ゆか (@yuka1093) February 23, 2023
鼻が大きく強調される文化的背景
青森の伝統工芸や郷土芸能では、誇張されたパーツに意味を込めることが少なくありません。鼻を大きく描くことで、勇猛さ・個性・魂の宿りを表現する手法は、ねぶた独特の表現文化。
昔の武将や鬼神の像にも、大きな鼻がよく登場します。つまり、見た目以上に“意味のある造形”ということなんですね。
ねぶた 顔の意味をもっと深く知りたい
なぜ「顔」はあそこまでデフォルメされる?
ねぶたの顔って、とにかく印象が強いですよね。これは人目を引くためのデザインであると同時に、「物語を伝える顔」であることも重要な役割なんです。
特に目・眉・鼻など、感情を象徴するパーツがデフォルメされることで、見た人の心にグッと残るよう設計されているそうです。
怒りや悲しみは顔で語られる
ねぶたに描かれる多くの登場人物は激しい感情を持つ人物や神様。その感情表現を、一番ダイレクトに伝えるのが「顔」なんですね。
なかでも鼻は、怒ったときに広がる鼻孔や、勇ましさを象徴する隆起として描かれます。実は、「鼻で語る」って表現、あながち間違ってないのかもしれません。
王林 解説 ねぶた 鼻の魅せ方に注目
王林さん自身の“青森愛”と解説の深み
王林さんは青森出身として知られていますが、解説中の一言一言からその郷土へのリスペクトが感じられました。「ここまで鼻にこだわってるの見てほしい」と語った時の目の輝き、印象的でしたよね。地元目線で語られるからこそ、よりリアルに伝わるんでしょう。
なぜ“鼻”がテレビで強調されたのか?
これはおそらくですが、**見慣れたねぶたの“新しい切り口”**として「鼻」に焦点をあてたのでは?という印象があります。視聴者に「えっ?なぜ鼻?」と思わせることで、興味を引き、文化や歴史に関心を持たせる狙いがあったのかもしれません。
まとめ
ねぶた祭の“鼻”がなぜ強調されていたのか、王林さんの言葉をヒントにひも解いてみました。単なる装飾ではなく、怒りや勇気を表現する象徴としての意味。普段は気づかないところに、ねぶた師たちの技術と情熱が込められていることに気づかされますね。
もし今年の祭りをテレビや現地で見る機会があったら、ぜひ「鼻」にも注目してみてください。その見方ひとつで、ねぶたの魅力が何倍にも膨らむかもしれません。


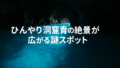
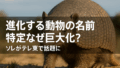
コメント