コンサートで当たり前のように使われるペン型ライト。でも「これって誰が始めたの?」と疑問に思ったことはありませんか?その答えが、今回の「チコちゃんに叱られる!」で明らかになるかもしれません。
2025年8月1日の「チコちゃんに叱られる!」で取り上げられるのが、“なぜペン型ライトを振るようになったのか?”という素朴な疑問。意外にもこの文化の始まりは、ある大スターの一言がきっかけだったそう。SNSでも話題になっており、昔のライブ文化を知らない世代にとってはまさに「そんな由来があったの!?」という驚きの連続になる予感です。今回はその背景を番組放送前に少し掘り下げてみます。
ペン型ライト振る理由
懐中電灯から始まった“応援の光”
実は、今でこそLED式や多色変更が当たり前のペン型ライトですが、始まりは1974年の西城秀樹さんによる大阪球場のコンサートだったと言われています。「お客さんの顔が見えなくて寂しい」と感じた西城さんが、ファンに向けて「懐中電灯を持ってきてください」と呼びかけたのが始まりだとか。その結果、客席に無数の光が灯る様子が生まれ、それが演出の一部としての“光を振る文化”に繋がったという説が濃厚です。
そうなんですよ‼️
ペンライトだけでなく
それ以外にも彼が始めたことが多数。
西城秀樹は今のライブの礎を作ったアーティストです https://t.co/3FDBOYiuOQ— crystal_love (@crystallove_h) July 8, 2025
そもそもなぜ“振る”必要があった?
照明機材が今ほど進化していなかった時代、光を振ることで演者に「ここにいるよ!」とアピールする意味も込められていました。また、周囲との一体感を高めたり、演出に合わせて光が揃うことで、会場全体がまるで舞台装置のように変化する。それが楽しくて、自然と広まったのかもしれません。
誰が最初に振ったの?
西城秀樹さんのライブ演出がルーツ?
西城秀樹さんが日本初のスタジアム単独ライブを行った大阪球場でのコンサート(1974年)が、ペン型ライト文化の最初とする説が有力です。ファンの顔を見たいという理由から光を使った演出を取り入れたという話は、近年になってNHKのドキュメンタリーでも紹介されました。「観客の存在を見たい」という気持ちから始まった演出が、今では応援の定番になっているなんて、なんだか素敵な話ですよね。
番組で何が明かされるのか?
NHKの番組案内には「伝説のコンサートがよみがえる!」との記述が。つまり、当時の映像や証言をもとに、西城秀樹さんのコンサートがピックアップされる可能性は高いでしょう。これまで“なんとなく”振っていたペンライトに、これほど温かい物語が隠れていたとは…。
チコちゃんで驚き判明?
あの演出が原点だったのかも
「チコちゃんに叱られる!」では、ただ知識を披露するだけでなく、「なるほど」と思える背景が丁寧に掘り下げられるのが魅力。今回のテーマでも、知られざる当時の文化背景や、演者とファンの関係性まで触れられる可能性があります。懐中電灯から始まったこの文化が、今のライブでどう使われているのか…放送を見ればきっと“応援の意味”が変わって見えるかもしれません。
昔と今、ペンライトの進化
当時の懐中電灯から、今はリモート制御式の多色LEDライトへと進化。ライブ会場で曲に合わせて色を変えたり、演出に統一感を出したり、ペン型ライトはまさに観客が作るステージ演出の一部になっています。
この文化、どう広がったの?
- ジャニーズ系:グループごとに“メンバーカラー”が設定され、色を合わせて振る文化が根付く。
- ハロプロやAKB系:コール&レスポンスやサイリウム芸との相性が良く、応援演出の一部として定着。
- アニソン系やK-POP:公式ペンライトが多く導入され、制御連動型の演出が主流に。
このように、もはやライブ文化の中で「ペン型ライトを振る」ことは無くてはならない存在に。あなたも一度は振ったこと、ありますよね?
ちょっと豆知識
ちなみに、ペン型ライトにはいくつかの呼び名があります。
- サイリウム(ケミカルライト)
- キンブレ(King Bladeの略)
- 公式ペンラ(公式グッズ化されたライト)
機材の進化とともに呼び名も変わり、応援スタイルもどんどん多様化しています。
まとめ
「誰が最初にペン型ライトを振ったのか?」という素朴な疑問の答えが、まさか1974年の西城秀樹さんのライブにあったとは驚きですよね。ただの応援グッズと思っていたペンライトに、ここまで深い物語があるとは思いませんでした。
「チコちゃんに叱られる!」の放送では、映像や証言を通じて、その文化の裏側が紹介されるかもしれません。放送を見たあとは、ライブでライトを振る時の気持ちがちょっとだけ変わるかもしれませんよ。
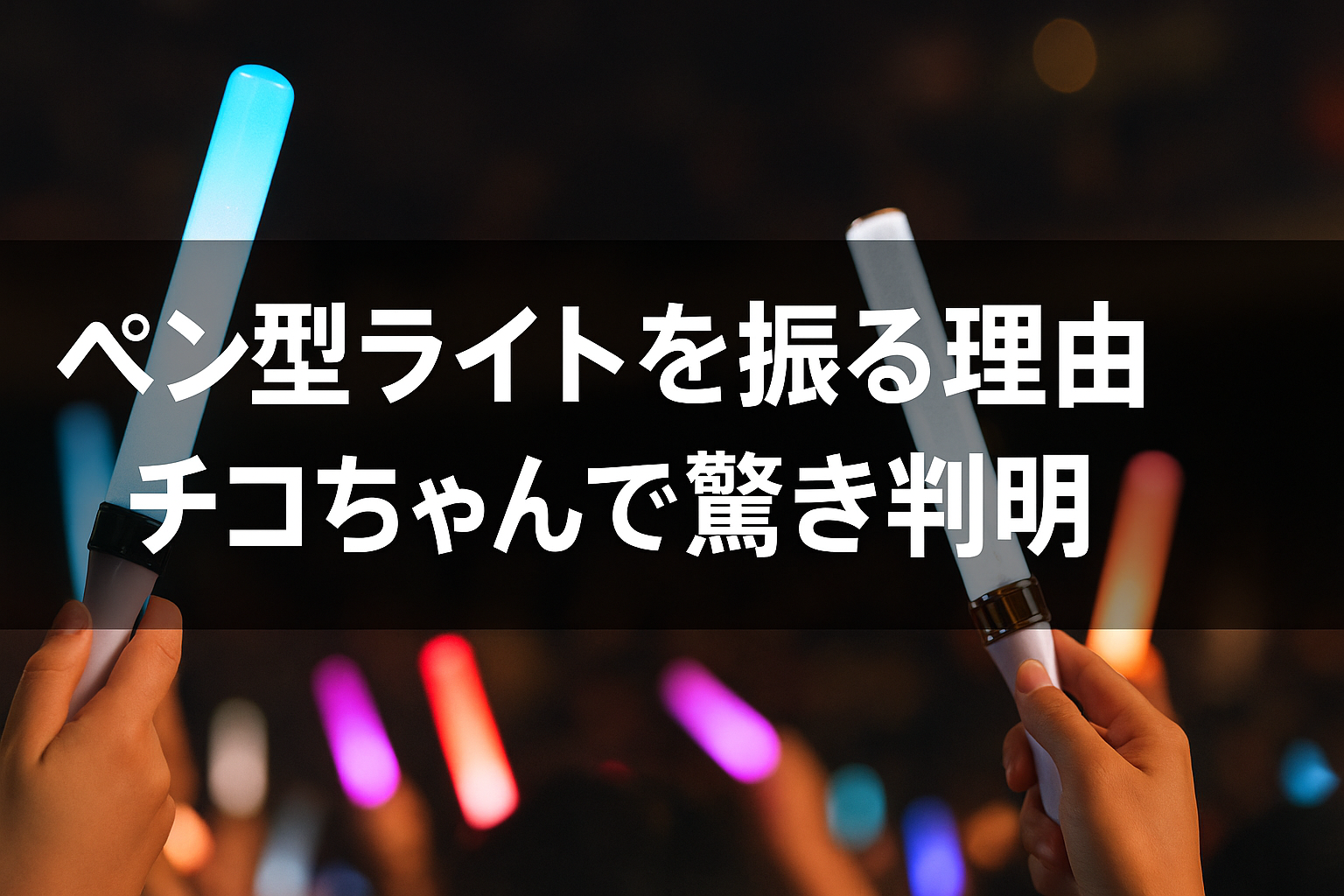

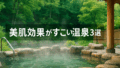
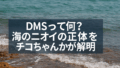
コメント