海のそばに行くと、ふわっと漂ってくるあの独特な香り。一度は「これってなんのニオイ?」と思ったこと、ありませんか?チコちゃんがその秘密をズバリ教えてくれました。
NHK「チコちゃんに叱られる!」で紹介された、海のニオイの正体。それはただの潮風ではなく、「DMS(ジメチルスルフィド)」という化学物質だというから驚きです。多くの人が海の香りに癒される一方で、その裏には微生物の営みや複雑な科学が関係しているんです。普段何気なく感じている香りに、これほど深い意味があるとは。今回はその“海の香り”の正体に、少しだけ詳しく迫ってみましょう。
海のニオイの正体はDMSだった
ジメチルスルフィドという物質
**DMS(ジメチルスルフィド)**は、プランクトンが死んだり分解されたときに発生する物質で、海のニオイの主成分として知られています。微生物が海藻を分解すると「DMSP」という物質が作られ、それがさらに変化してDMSになります。この香りは“磯の香り”と呼ばれることもあり、多くの人が「海の香り」として無意識に覚えている成分でもあるんです。
地中海は水が綺麗なところが多くて助かる。磯の匂いはほぼしない。
あの磯の香りって植物性プランクトンの死骸から発生する成分らしいよ。
ジメチルスルフィド(DMS)
Sulfure de diméthyle pic.twitter.com/MEDCeUMIGM— Rin🇫🇷フランスで自由気まま (@Linlin_fr) April 21, 2023
海沿いを歩いていてふわっと香る、あの爽やかで少し生臭さもある香り。その実態がこんな科学反応によって生まれていたなんて、ちょっと驚きですよね。
人間はなぜこのニオイを心地よいと感じる?
実はこのDMS、私たちの脳に“懐かしさ”や“安心感”を与えるとも言われています。過去の経験と結びつきやすく、幼い頃の夏の海水浴や潮干狩りの記憶を呼び起こすこともあるそうです。
また、DMSは海鳥や魚たちにとっても重要な“サイン”のようなもので、エサが豊富な場所を知らせてくれる信号にもなっています。まさに「香りでつながる海の世界」と言えそうです。
海のニオイはどこで感じられる?
海岸だけじゃないDMSの出現場所
海のニオイは海岸だけでなく、干潟や漁港、さらには潮の香りを再現した温泉地などでも感じられます。例えば、和歌山県の勝浦温泉や、千葉県の銚子などでは「潮の香りがする」と話題になることも。
さらに、磯焼けが進んでいる地域ではDMSの発生量が減って香りが薄れているという話もあり、ちょっとした環境変化にも敏感なんですね。
似たような香りがする意外な場所
少し意外なところだと、腐りかけのキャベツや硫黄泉の温泉にも似たような香りを感じることがあります。これはDMSと似た構造の物質が関係していて、どこか“生臭くてツンとする香り”という共通点があるからです。
この特徴を利用して、食品業界ではDMSの香りを人工的に加えることもあるんだとか。まさかあの香りが商品開発にも活かされていたとは、驚きですね。
DMSは健康に影響あるの?
気になる安全性について
ジメチルスルフィド自体は通常の濃度では健康に問題はありません。むしろ、低濃度であればリラックス効果があるとも言われています。とはいえ、閉じた空間で濃度が高くなれば刺激臭として感じることもあり、工業的には注意が必要とされています。
「嗅ぐ」ことで見えた #海洋プラスチック 問題の真実
t.cohttps://t.co/fxijE0sW04— MOLp(そざいの魅力ラボ) (@MCI_MOLp) March 21, 2025
日常生活で海辺を歩くくらいではまったく問題ないので、安心して大丈夫ですよ。
海とともにある暮らしの一部として
DMSの香りを知ることで、私たちが海とどれだけ深く関わって生きてきたかを感じられるようになります。科学的には難しくても、自然の中の“香りの物語”として捉えると、より親しみが持てますよね。
たとえば、海沿いのカフェで風を感じながらお茶を飲むとき、釣りをしている最中にふと香ってくるあのにおいに、ちょっと注目してみるのもいいかもしれません。
まとめ
チコちゃんが教えてくれた「海のニオイ」の正体、DMS(ジメチルスルフィド)。一見ただの磯の香りかと思いきや、そこには海の微生物たちの働きや、生態系のバランス、さらには私たちの記憶とつながる香りの力が秘められていました。
何気ない海辺の散歩が、少しだけ豊かに感じられるようになる。そんな小さな気づきが、日常をちょっと楽しくしてくれるんじゃないでしょうか。
※本記事は番組放送前の情報をもとに構成しており、放送内容と一部異なる可能性があります。


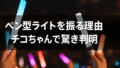

コメント