NHK「知恵泉」で取り上げられる島津重豪さん。その参勤交代が“寄り道だらけ”だったという話、ちょっと気になりますよね。制度に縛られた江戸時代において、なぜそんな自由な行動ができたのでしょうか。
島津重豪さんは“蘭癖大名”とも呼ばれ、薩摩藩を率いた人物です。オランダや中国の知識を積極的に吸収したその姿勢は、現代でも注目されています。今回の「知恵泉」では、彼の“参勤交代での寄り道”に焦点が当たります。ただの寄り道ではなく、国際交流や情報収集の意図すらあった可能性があるのです。こうした視点から、番組で語られる内容をひと足先に深掘りしてみましょう。
なぜ島津重豪さんは寄り道したのか?
参勤交代中の立ち寄り先には戦略があった?
通常、参勤交代は江戸と領地を往復するだけの行程です。しかし島津重豪さんは、宇治の黄檗宗寺院や長崎の出島など、外交・知識ネットワークの拠点となる場所を巡っていました。
島津重豪:大河「べらぼう」にも登場 薩摩藩を一流に押し上げた“知恵” 外国大好き! 真の思惑とは?#島津重豪 #先人たちの底力 #知恵泉 https://t.co/XRHP74B7HN
— MANTANWEB/毎日キレイ (@mantanweb) July 29, 2025
たとえば、黄檗宗寺院では中国語に通じた僧と接点を持ち、長崎ではオランダ商館長と接触。これ、たまたま通ったとは思えませんよね?まるで現代の視察旅行のようです。
黄檗宗萬福寺
中国から渡来した隠元禅昌師開創。
古筝を聴く為に足を運んだけど、寺院の佇まいに時間を忘れた。
そして、300年以上の伝統ある普茶料理も感激!
隠元禅師は、いんげん豆、すいか、蓮根等々、様々なものを日本に伝えたらしい。
宇治にある落ち着きのあるよいお寺 pic.twitter.com/GkVhgfFmoV— ゆうゆ🎗️ (@chuntian0406) May 14, 2024
自由な“寄り道”を可能にした背景とは?
薩摩藩は幕府から見ても一目置かれる大藩でした。島津重豪さんが文化交流や学問という名目を立てたことで、ある程度の自由が許容されていたと考えられます。さらに彼は琉球王国を通じて北京の医師に薬草の鑑定を依頼するという、裏ルートを使った情報収集も実施。これって、今で言えば国際コンサルタント的な動きにも見えますよね。
はいさ〜い🌅
私の志
【琉球に住む人が平和に暮らし、未来に希望が持てる】を実現し、琉球の地域創生を成し遂げるため
本日も沖縄県から琉球の魅力を発信✨
誠心誠意頑張ります🙌
『首里城』
沖縄のシンボル☀️琉球王国の歴史と文化がぎゅーっと詰まった、まさに生きた博物館なんです🏯 pic.twitter.com/kNz9GACV6b
— 琉球物語 琉球の魅力を全国に🌻 《沖縄県地域創生》 (@ryukyu_story) July 11, 2025
“蘭癖大名”という呼び名に込められた意味
蘭癖とは単なる好奇心じゃない
“蘭癖大名”とは、オランダ文化に強く興味を持った藩主を指す言葉ですが、島津重豪さんの場合、その関心は医療・自然科学・語学にまで及んでいました。これは単なる趣味の域を超えたもの。
藩の未来を見据えた先見性が感じられます。たとえば、シーボルトさんとも3度会見し、直接交流を深めたという記録も残っています。
なぜ“浮いた存在”が今注目されているのか
当時の武士階級では、こうした動きは“風変わり”と見られていたかもしれません。でも、今ならどうでしょう?異文化への柔軟な理解力と実行力は、まさにグローバルリーダーの資質です。
実際、最近では企業のリーダー層も島津重豪さんのような「枠を超える行動力」をモデルに挙げるケースもあるんです。
【トレンドが人気を集めている理由】
- 歴史人物の“裏側”を描く構成が増え、人間味ある視点が求められていることや
- 国際交流×行動力×柔軟性という現代ニーズにマッチしているなど
- 規則に縛られないリーダー像がZ世代や若年層に共感を呼びやすいことです
【日常生活への活用提案】
- 歴史を「人物目線」で読むことで、会話のネタにもなりますよね
- 旅行先で「寄り道力」を意識してみると結構新しい発見がありますからね
- “行動に意味を持たせる”姿勢は、仕事のモチベーションにも活かせますよ
最近では磯田道史さんも「蘭癖大名」の分析に言及し、現代の外交リーダーと比較するコラムを寄稿していました。
【まとめ】
“寄り道だらけ”の参勤交代は、島津重豪さんにとって単なる旅ではなく、情報と人脈を得るための戦略的な行動でした。蘭癖大名という言葉に揶揄的な意味が込められていたとしても、彼の視線の先には確かな“未来”がありました。
NHK「知恵泉」でこの側面が取り上げられるのは、その先進性に価値があるからこそ。番組を見る前に、その背景を知っておくだけでも、きっと視聴の深さが変わってくると思います。
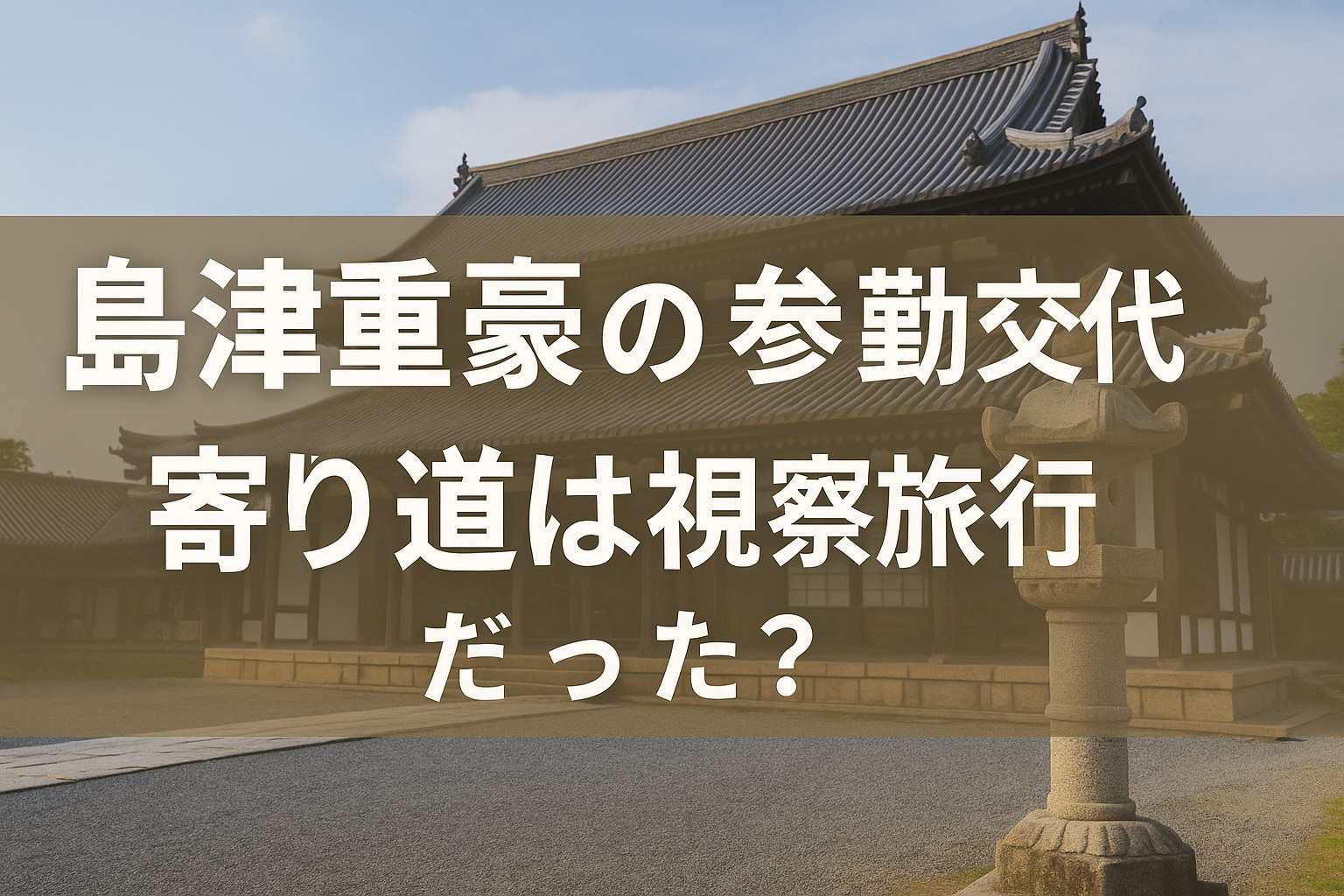
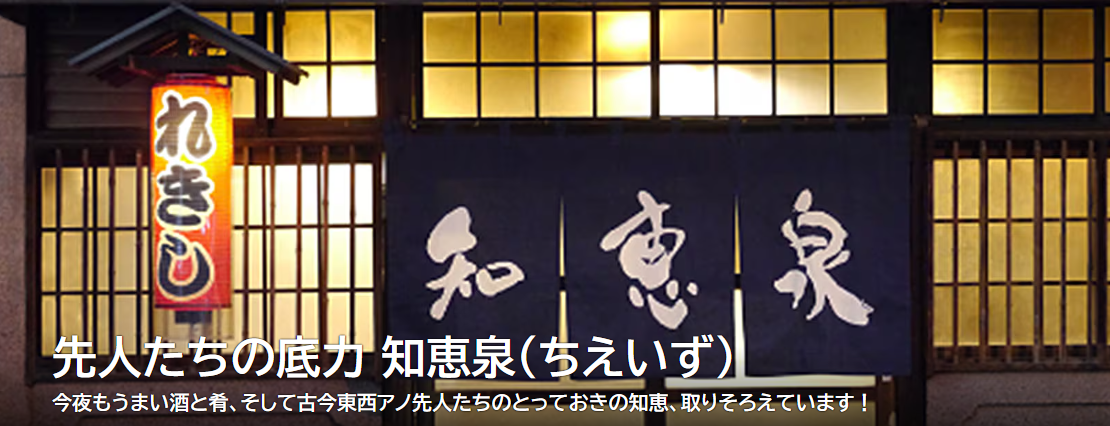
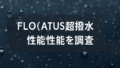
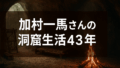
コメント