4月22日放送予定の『知恵泉』では、小泉セツさんにスポットが当たります。今回は放送前の情報に基づき、彼女の出身地や生涯のルーツに優しく寄り添いながら、その足跡をたどっていきます。
小泉セツさんは、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)を支えた妻として知られています。彼女は単なる“内助の功”ではなく、日本の民話や伝承を八雲に語り伝えた文化の架け橋的存在でした。特にその語り部としての才能は、現在において再評価が進んでいます。
今回の『知恵泉』で焦点が当たることで、「彼女の人生にもっと深く触れたい」と思う方も多いのでは無いでしょうか。そこで本記事では、彼女の出身地・松江とその背景に迫り、温かく具体的に紹介していきます。
小泉セツ 出身地とルーツ
松江市役所で小泉セツさんがお話ししておられた! #ばけばけ 楽しみ!!! pic.twitter.com/UFabGVweh0
— ヘイソン・ニャー (@heison_nya) January 31, 2025
出雲松江で生まれ、養子として育つ
小泉セツさん(戸籍名:小泉セツ/本人使用名:節子)は、1868年2月26日(慶応4年2月4日)、出雲国松江(現・島根県松江市)に生まれました。父は松江藩の家臣であった小泉弥右衛門湊。
ただし、生後わずか7日で親戚筋の稲垣家に養子に出され、松江の庶民的な環境で育ちました。明治維新により士族が没落し、11歳で機織り工場に出るなど、少女期は苦労が多かったようです。
八雲との出会いまでの波乱の人生
18歳で結婚したものの、夫・前田為二の出奔によりわずか数年で離婚。22歳でシングルとなった小泉セツさんは、1891年2月、小泉八雲宅の住み込み女中として働き始めました。
3/24発売の新刊をご紹介いたします。
『小泉八雲 ラフカディオ・ヘルン』
田部隆次小泉八雲の全生涯を直弟子が綴る伝記の決定版。
坪内逍遙、西田幾多郎らの序、八雲夫人・小泉節子(セツ)の「思い出の記」を収録。〈解説〉池田雅之 pic.twitter.com/AepRsjh4DK— 中公文庫(中央公論新社) (@chuko_bunko) March 21, 2025
そして同年7月には、事実婚の形で八雲との生活をスタート。後に正式に結婚し、松江から熊本・東京と共に移住しながら生活を築いていきました。
小泉セツ 松江に残る記憶を辿る
文化の橋渡し役としての功績
小泉セツさんは、夫の創作活動を多方面から支えました。日本語が流暢ではなかった小泉八雲との日常的な意思疎通を支えただけでなく、松江の伝承民話や風習を覚えて語ることで、小泉八雲のインスピレーション源となったのです。
民話の収集、原稿の清書、資料整理などの実務支援もこなし、まさに“文化の通訳者”ともいえる存在でした。まさに共同なんちゃら的存在ですよね!
『怪談』の影にあった語り部の力
たとえば『怪談』や『知られぬ日本の面影』に収められた物語の多くが、小泉セツさんの語りに由来しています。特に「耳なし芳一」や「雪女」といった話には、彼女が記憶と声で継承した“日本の風”が感じられます。
1890年の今日、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)来日。有名な『耳なし芳一のはなし』『雪おんな』など、文献や民間伝承に取材して創作された短篇集は、人間に対する深い洞察に満ちています。
『怪談』☞ https://t.co/iKc5fE5lYa
『雪女 夏の日の夢』☞ https://t.co/P0iVbakEfQ pic.twitter.com/LVoZqRvfUB— 岩波書店 (@Iwanamishoten) April 4, 2025
記憶に頼るオーラル・ヒストリー形式で八雲に伝えられたこれらの話は、彼の文体に深みを与え、世界中の読者を魅了し続けているのです。彼女無しでは小泉八雲はどうなっていたのでしょうね?
晩年と再評価の動き
『思い出の記』と記念館での常設展示
小泉八雲の没後、小泉セツさんは1926年に回想録『思い出の記』を執筆。そこでは夫婦の生活、創作の裏側、そして当時の日本社会への想いが静かに綴られています。
八雲忌の本日9月26日
妻・小泉セツが八雲との思い出を綴った『思ひ出の記』
企画展「小泉セツ ラフカディオ・ハーンの妻として生きて」図録2冊を同時発売しました📚
記念館ミュージアムショップにてお求めいただけます https://t.co/bYi9aBtrhW pic.twitter.com/Vdv8xnayvw— 小泉八雲記念館 (@hearnmuseum) September 26, 2024
現在では、松江市の小泉八雲記念館にて彼女に関する常設展示が行われており、愛用品や直筆資料が展示されています。
経済的苦境と最期の日々
夫の死後、著作権収入で暮らしていた小泉セツさんでしたが、昭和初期の不況で生活が困窮。家財を質に入れながらも家計を守り、1932年、東京・西大久保の自宅で64歳の生涯を閉じました。現在は、東京都豊島区の雑司ヶ谷霊園にある小泉八雲と並んで眠っています。
ギリシャ出身の新聞記者/作家で日本民俗学研究の第一人者、小泉八雲(出生名:パトリック・ラフカディオ・ハーン/Patrick Lafcadio Hearn)さんのお墓。
「都立 雑司が谷霊園」
あべっくすの「昼間の路地裏さんぽ」 pic.twitter.com/2dD2mXwwJ0
— ABE U-ichi (kamex) (@kamex) December 17, 2020
まとめ
小泉セツさんは、明治という激動の時代を生き抜き、文化の橋渡し役として知られざる貢献を果たしました。
彼女の足跡は、今も松江の町や記念館に息づいています。
放送前の今、彼女のルーツをたどることで、きっと番組の感動が深まると信じています。
お見逃しなく!

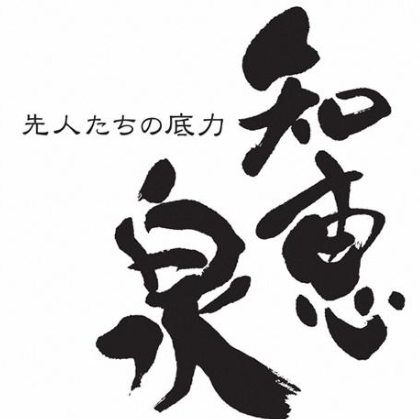


コメント