時代劇でおなじみの**「水戸黄門」。でも“黄門”って何のこと?言われてみるとよくわからないまま通り過ぎてきた気がしませんか?今回の「チコちゃんに叱られる!」**で取り上げられるということで、気になるその正体を一緒に探ってみましょう。
なんとなく耳慣れた**「水戸黄門」という呼び名。でも「黄門」ってどういう意味?と聞かれると、すぐに答えられる人は少ないかもしれません。
しかも、佐々木助三郎さんや渥美格之進さん**として登場する“助さん格さん”にも、実はモデルがいたとか?今回のチコちゃん放送では、そんな素朴だけど奥深い疑問に切り込むようです。
番組をより楽しむために、予習として押さえておきたい話をまとめてみました。
水戸黄門黄門とはの真実 実は公的な役職名だった?
「黄門」ってそもそもどういう意味?
「黄門」という言葉、実は中国の唐の時代の役職「黄門侍郎」に由来しています。これは皇帝の近くで働く偉い人、というイメージです。
日本では、その唐風の名前が「中納言」の呼び替えとして使われるようになり、徳川光圀さんが中納言だったことで「水戸黄門」と呼ばれるようになったんですね。
ちょっと堅い話ですが、要するに“格の高い人”だったということ。聞けば納得、でも知ってる人は意外と少ないのでは無いでしょうかね?
「水戸黄門」は光圀さんだけじゃなかった?
実は「水戸黄門」と呼ばれる資格があるのは徳川光圀さんだけではありません。水戸藩主の中で中納言の官位を持った人は全部で7人いて、その全員が「水戸黄門」と呼べる立場だったそうですよ。
つまり、「黄門さま=光圀さん」というのは、あくまで時代劇のイメージなんです。ちょっと驚きますよね。私がこれ知ったときはエ~~!!でしたよ。
助格の謎もチコちゃんで再注目
助さん格さんって実在したの?
ドラマに出てくる助さん格さん。実はこれも完全な創作ではありません。
モデルとされているのは、佐々宗淳さん(助さん)と安積澹泊さん(格さん)という学者たち。どちらも水戸藩の学問所「彰考館」で要職を務めた、知識人だったんですね~。
学者の名前がドラマで“強いお供”にアレンジされるって、なんだか面白い発想ですよね~。
ドラマと史実の違いに驚き
実際の佐々木助三郎さんや渥美格之進さんは、刀を振り回して旅する武士ではなく、文献をまとめたり藩政を支えたりする役目。全国漫遊の旅も事実ではなく、演出として作られたものなんです。
それでも、人々の記憶に残るキャラクターになったというのは、ある意味すごいことだと思いませんか?
他にも気になる歴史的背景
「副将軍」って本当に存在した?
時代劇でよく出てくる「天下の副将軍・徳川光圀さん」という紹介。でも実際、江戸幕府に「副将軍」という役職は存在しませんでした。ん~残念!!💦
これはドラマの中で“正義の象徴”っぽく演出するための表現のようです。
こうした演出が、歴史のイメージづくりに影響を与えてきたのだとすると、時代劇って本当に力がありますね。当時の時代背景等も善悪物が脚光を浴びる背景となっていたのかも知れませんね~?
「黄門」は光圀さんだけの称号ではない?
現代では「水戸黄門」といえば徳川光圀さんを指しますが、「黄門」というのはあくまで中納言の唐名。平安時代には「平の黄門」なんて呼ばれた人物もいたんですよ。
つまり、“黄門”というのは広く使われていた言葉だった、ということなんです。意外と知らない人、多いかもしれませんね。
まとめ
「水戸黄門」って、ただのあだ名じゃなかったんですね。
中納言という官職名に由来していて、他にも同じ称号を持つ人がいたとは驚きです。
助さん格さんも学者だったなんて、知らなかった人にこそ届いてほしいお話です。
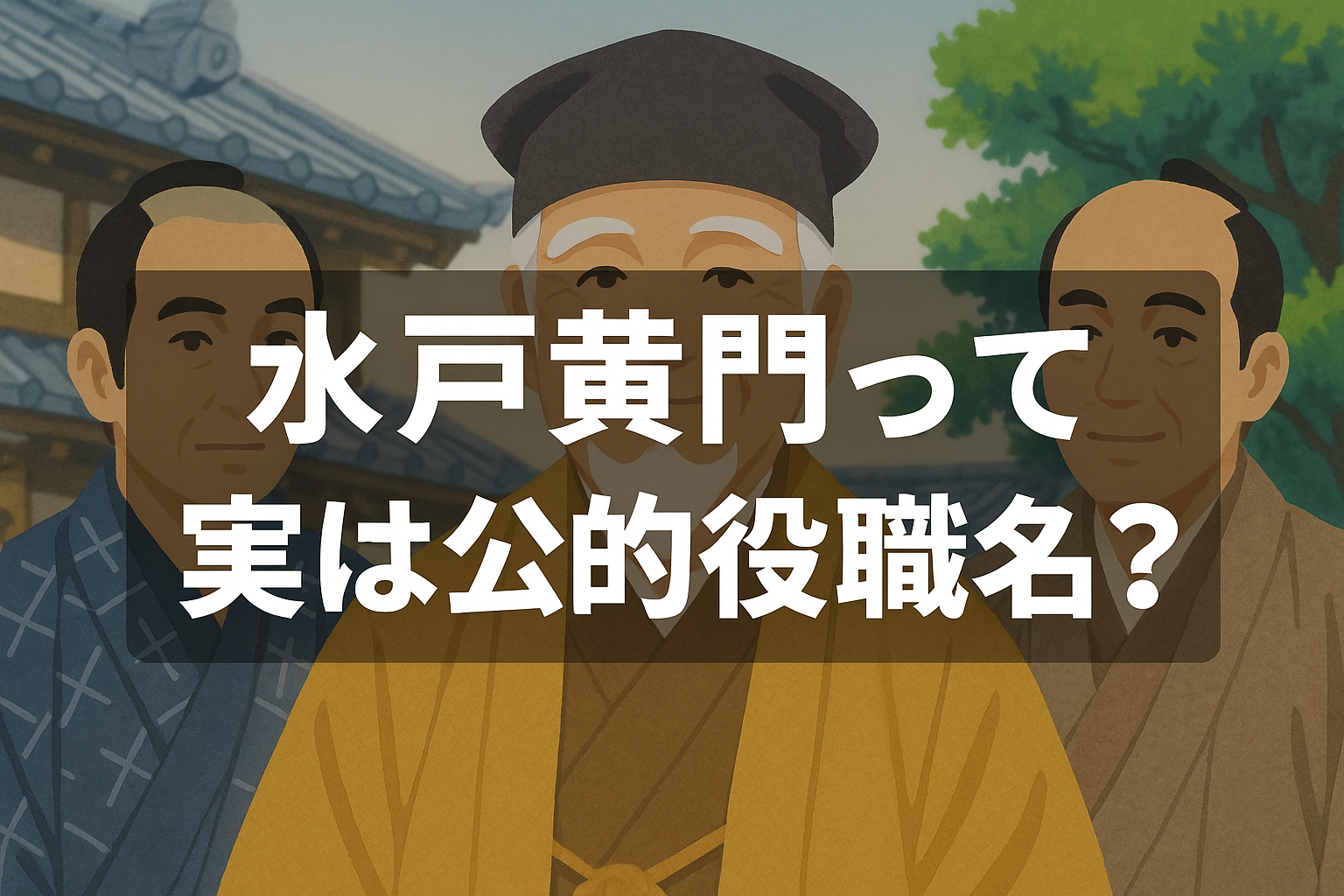

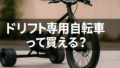
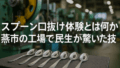
コメント