「ゲリラ豪雨ゲリラじゃない誰が言い出した?」という言葉が『マツコの知らない世界』で取り上げられたことをきっかけに、じわじわと注目を集めています。ただ、この言葉、実は正式な気象用語じゃないんです。この記事では、放送前の段階で分かっている情報をもとに、その背景や言葉の由来を探ってみたいと思います。
ゲリラ豪雨って、誰が言い出したの?
「ゲリラ豪雨」という響き、なんとなくは分かるけれど、誰が使い始めたのかは案外知られていませんよね。調べてみると、どうやらこの言葉、2000年代頃にメディアが作った造語だそうです。
つまり、誰かひとりの名付けではなく、テレビや新聞が「突然の激しい雨」をインパクト重視で伝えるために、軍事的な「ゲリラ戦」に例えて使い始めた、という流れなんですね。
ゲリラ豪雨による雨柱。
あまりに局所的に過ぎる。
災害を装った人工的な兵器……の実験ではないのか? pic.twitter.com/RCpgdQtlvW
— U (@wayofthewind) July 10, 2025
でも、「じゃあ誰が?」となると、明確な答えは無いんです。よく聞くのに、出どころが不明──そこがモヤっとするポイントなのかもしれません。
「ゲリラ」って、そもそもどんな意味?
“ゲリラ”と聞くと、多くの人が「突然、予測できない攻撃」のようなイメージを持つのではないでしょうか。実際には、**軍事用語としての“奇襲攻撃”**を意味する言葉です。
そんな強い語感を持つ言葉が、天気の表現に使われるのって、ちょっと不思議な感じがしますよね?その違和感、実は多くの人が抱いていたようです。
この違和感に触れたのが、番組内でのマツコ・デラックスさんの一言。「なんで“ゲリラ”なの?」という素朴なツッコミが、多くの人の心に引っかかったんじゃないでしょうか。
マツコ・デラックスさんの“ツッコミ”が話題に
『マツコの知らない世界』で、マツコ・デラックスさんが「ゲリラ豪雨っておかしくない?」と語るシーンが予告されました。
この発言、実は多くの人の心を代弁していたのかもしれません。普段から当たり前のように使っていた言葉が、改めて問われると「確かに…」と気づかされますよね。
こういう「小さな違和感」にスポットを当ててくれるのが、マツコ・デラックスさんらしい鋭さ。そして、その気づきが、視聴者の検索行動にもつながっているようです。
今、「ゲリラ豪雨」が検索されるワケ
- 正体不明だからこそ気になる:誰が言い出したのか分からない言葉は、ちょっと調べたくなるもの。
- 使ってるのに意味を知らなかった:なんとなく理解してたつもりが、実はあいまいだった…そんな瞬間ってありますよね。
- マツコ・デラックスさんの発言が共感を呼んだ:「それ、思ってた!」と感じた人も多かったのでは。
気象庁が「ゲリラ豪雨」を使わない理由
実は、気象庁では「ゲリラ豪雨」は使っていません。その理由は明快です:
- 誤解を招きやすく、意味があいまい
- 攻撃的で不適切な語感がある
- 最新の気象技術で、実際には予測できることもある
たとえば「局地的大雨」や「集中豪雨」などの表現が、気象庁では使われています。こちらの方が、聞き慣れないかもしれませんが、より正確で実用的なんですね。
言葉を知ると、見える世界がちょっと変わる
何気なく使っている言葉の背景を知ると、日々のニュースや天気予報の見え方も変わってきます。
- 気象ニュースの読み解き力がつく
- 防災意識が自然と高まる
- 子どもとの会話のタネにもなる
「ゲリラ豪雨」って、なにげない言葉のようでいて、実は私たちの暮らしに深く関わっている言葉だったりするんです。
関連の話題もちょっとだけご紹介
最近話題になっているのが、雲の専門家・荒木健太郎さんによる天気と雲の見方。書籍やテレビでの解説がとても分かりやすくて、子どもから大人まで人気です。
光文社新書『雲を愛する技術』の荒木健太郎さんが、「マツコの知らない世界」にご出演🙌
明日です😊 https://t.co/qdACJcf53K— 光文社 プロモーション部 (@kobunsha_promo) July 14, 2025
また、ウェザーニュースのアプリでは「ゲリラ豪雨予測通知」の制度が年々アップしていて、ちょっとしたお守り代わりになっている人も多いようですよ。
まとめ:気づきのきっかけは、いつも身近なところに
「ゲリラ豪雨ゲリラじゃない誰が言い出した?」という問いかけから始まった今回の話。
その答えは、はっきりしない部分もあるけれど、「なんとなく気になっていたこと」を改めて見つめ直すきっかけになる──それが今回の大きな収穫なのかもしれません。
言葉って、ただのラベルじゃなくて、時代や価値観、社会の空気を映す鏡でもあります。だからこそ、見直してみる価値があるんです。
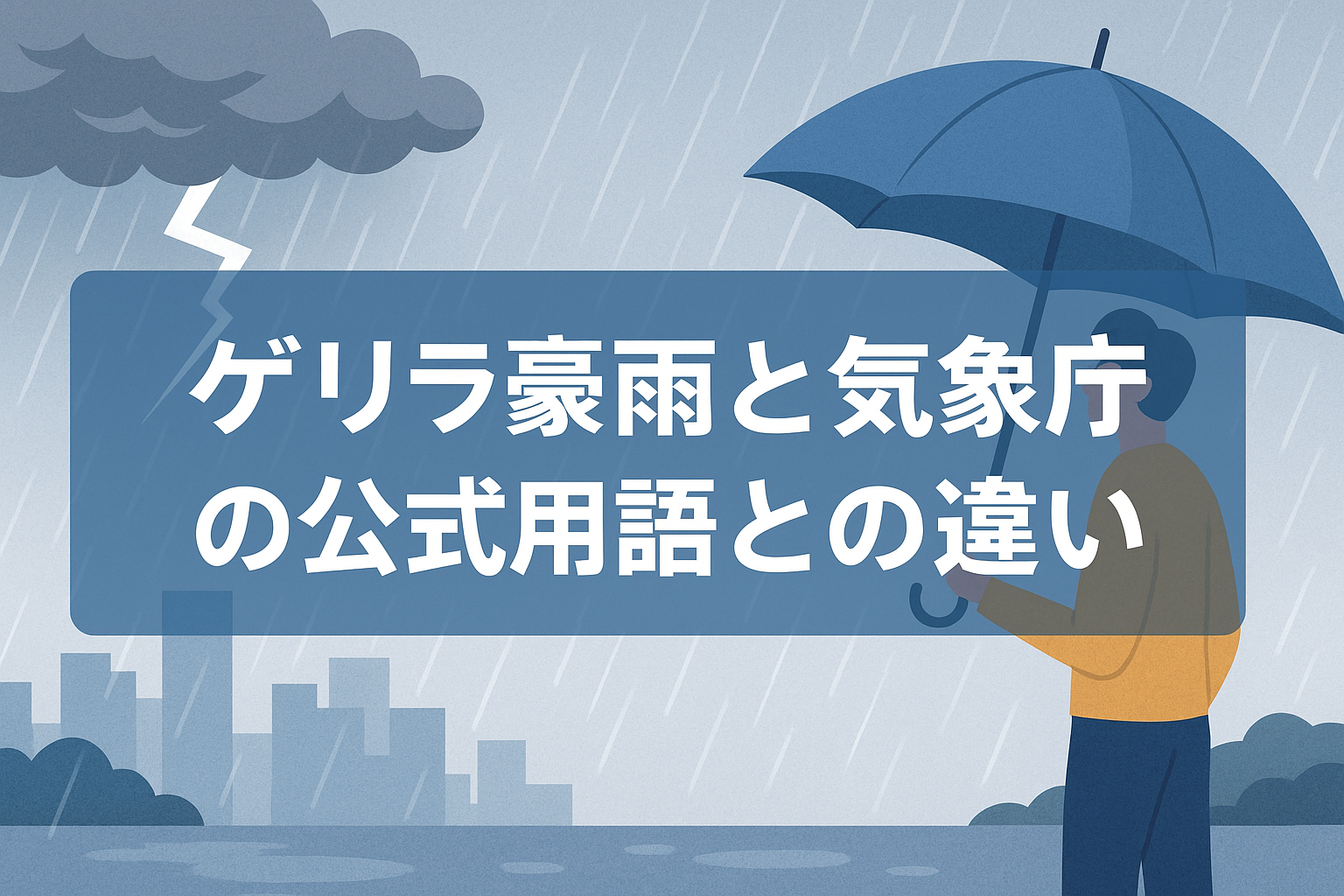

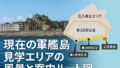

コメント