「蛇」や「蛙」などの動物に“虫偏”がついてるって、ちょっと不思議だと思いませんか?5月放送予定のテレ東特番『何を隠そう…ソレが!』では、そんな動物漢字の謎が紹介されるようです。番組前にちょっと気になるポイントを整理しておきましょう。
今回の放送では、虫偏が付く理由として「得体の知れない生き物だから」という説明がありそうですが、それだけだとちょっと引っかかりますよね?
実は、古代中国の言語観や漢字に込められた感覚的な判断が背景にあるんです。
あの見慣れた漢字の裏に、そんな意味が隠れているなんて…ちょっと面白くありませんか?この記事では、そうした気づきを中心にご紹介していきます。
動物漢字に虫偏が付く理由
虫偏は「昆虫」だけじゃなかった!
日常で目にする動物漢字の中には、虫偏がついているのに虫じゃない動物がけっこうあります。
たとえば**「蛇」や「蝦」、「蛸」**。実はこれ、昔の人たちが“なんだかよくわからない生き物”と感じていたものに虫偏をつけていた名残なんです。
「気味が悪い」「どこにでもいる」「素早く動く」など、感覚的なものが関係していると言われています。
見た目や動きが判断基準だった?
漢字の成り立ちには、理屈より感覚が優先されていたことも多いんです。たとえば、夜に活動する、地を這う、ぬめっとしている…そんな生き物には「虫」としての要素を感じ取ったのかもしれません。
蛙(かえる)や蝙蝠(こうもり)、**蜃(しん)**などがその代表格。生物学的な分類じゃなく、“どう感じたか”が漢字に表れているって、ちょっと面白いですよね。
見慣れた字に隠された言語の警戒心とは?
「虫」がついてると怖く見える理由
たとえば**「蛾(が)」や「蛭(ひる)」**って、なんとなく不気味に感じませんか?それって、もしかしたら漢字の構造がそう思わせてるのかも。
昔の人が「警戒しておいたほうがいい生き物」って意味を込めて虫偏を使っていたとしたら、文字そのものが注意のサインだったのかもしれません。
番組では語られない“文字の深層”
今回の番組でも「虫偏は不思議な動物につく」という紹介はあると思いますが、なぜそうなったのかまでは触れられない可能性もありますよね。
実際には、「分類しづらい」「何だか得体が知れない」…そんな感覚を記号にしたのが虫偏。現代の分類とは全然違う、古代の価値観が可視化された文化遺産とも言えそうですね。
動物漢字は“鳴き声”から生まれたものも多い?
音の響きが文字になったって知ってた?
一部の動物漢字は、その生き物の鳴き声がもとになって作られたものなんです。
たとえば**「鴉(カラス)」は「ガーガー」→「牙(ガ)」+「鳥」、「鳩」は「クックー」→「九(ク)」+「鳥」、「鴨」**も「コウコウ」→「甲」が語源と言われています。
鳴き声を文字にする発想、ユニークですよね。
羽音や雰囲気もヒントに?
**「蚊(か)」は羽音の「ブーン」から「文(ブン)」を使って「虫+文」、「猫(ねこ)」**は「ミャー(ウ)」を「苗」で表して「犭+苗」に。こうやって考えると、昔の人の耳と感覚がそのまま漢字に残ってるみたいで、ちょっとロマンすら感じます。
まとめ
普段使っている動物漢字にも、「虫偏」や「鳴き声」がもとになっているものがあるって知ると、漢字が少し身近に感じませんか?
テレビではサラッと流されがちなところを、こうしてじっくり見ていくと、言葉に込められた人間の感覚や文化が見えてくるのもおもしろいですよね。


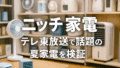
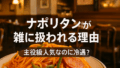
コメント