イタリアから来日した風鈴職人志望のエレナ・ロッシさん。美しい風鈴を作る彼女の悩みは、「音が鳴らない」こと。その答えを探しに、彼女は日本の伝統工芸に飛び込みました。そこには、職人の感性と情熱が響き合う世界が待っていたのです。
出典:https://www.tv-tokyo.co.jp/nipponikitaihito/?cx_search=program&
『世界!ニッポン行きたい人応援団』で紹介されたエレナ・ロッシさんの挑戦は、単なる文化体験ではなく、“音が鳴らない”という深い悩みに向き合う姿でした。
日本の職人たちと触れ合いながら、津軽びいどろや鍛造風鈴の奥深さを知っていく過程は、視聴者にとっても「風鈴の音って、そんなに繊細なの?」という新たな視点を呼び起こします。
この記事では、番組で描かれた“音が鳴らない理由”を少し丁寧に深掘りしてみます。
エレナの悩み「音が鳴らない」風鈴とは?
なぜ音が出ない?その原因を探る
エレナ・ロッシさんがイタリアで作っていた風鈴は、見た目こそ綺麗だったものの、期待していたような風鈴の音色が響かないことが悩みの種でした。風鈴は、素材や厚み、舌のバランス、吊るし方などの細かな要素が絡み合って初めて、あの澄んだ音が生まれます。
特に「日本のような音を再現したい」という思いが強かった彼女にとって、その“鳴らない”という現象はとても深刻だったようです。あなたなら、どこに原因があると考えますか?
音色を生み出す要素と課題
そもそも風鈴の音は、舌が本体に当たったときに発生しますが、その素材や当たり方ひとつで印象はガラッと変わります。
たとえば、舌が重すぎると響きにくくなりますし、吊るし糸の長さや太さでも音の立ち上がりが変わることも。こうした微調整の積み重ねが、ガラス風鈴の“あの音”を作り出しているんですね。
私自身、「こんなにも感覚的なものだったのか」と驚きました。
応援団が用意した日本の技と知恵
津軽びいどろ工房での学び
青森の津軽びいどろ工房では、エレナ・ロッシさんが直接職人から「音を整える技」を体験します。厚みを均一にすることや、ガラスの膨らみのわずかな違いが音の伸びに影響することなど、一見すると目に見えない違いが、耳にはっきりと伝わるという事実に、彼女も驚いていたようです。
ちなみに、某有名インテリアブランドでも津軽びいどろ風鈴の取り扱いが話題になったことがあります。ものづくりの世界は、目ではなく“耳”で判断する場面もあるのだと感じさせられました。
鍛造風鈴との出会いと感動
鳥取の鍛造風鈴工房では、和釘を使った金属製の風鈴を体験。叩いて作る過程の中で、素材の密度や形によって音の余韻や響きが大きく変わることを知ります。ガラスとはまた違う、どこか重みを感じる音にエレナ・ロッシさんが聞き入っていたのが印象的でした。
まさに“耳をすませば響く音の奥行き”といえる世界。あなたは、ガラスと金属、どちらの音に心を動かされますか?
エレナがたどり着いた“答え”とは
音を響かせるのは技術と感性
職人たちが行っていたのは、「素材を整える作業」というより、「音を育てる仕事」に近いのかもしれません。エレナ・ロッシさんが学んだのは、技術だけでなく、どんな音を鳴らしたいかという“感覚”そのもの。
ほんの少しの角度や厚みの差が音に与える影響を、耳と手で確かめながら作っていく工程が、まさに日本の工芸の真骨頂とも言えます。音が「鳴る」のではなく「響く」瞬間、その場の空気まで変わるような感覚を覚えました。
理想の音が鳴った瞬間
実際に完成した風鈴を鳴らした瞬間、エレナ・ロッシさんの顔に笑顔が戻ります。あの「これだ」という音に出会えたとき、彼女は“音が鳴らない”という壁を、自分の手で乗り越えたことになりますよね。見ている側としても「その音を聞かせて」と思わず口にしたくなるような感動がありました。
■ 音が響いた、その瞬間に
エレナ・ロッシさんが“鳴らない風鈴”という悩みに向き合ったこの旅は、単なる工芸体験ではなく、感性そのものと向き合う時間だったのかもしれません。
ガラスと金属、それぞれの音に耳を傾け、職人の手の中で音が育まれていく様子は、見る側の心にも響いてきました。
番組を通して見えてきたのは、「音」とは物理現象以上に、人の想いが宿るものだということ。あなたも、今夜は少しだけ風鈴の音に耳を澄ませてみませんか?
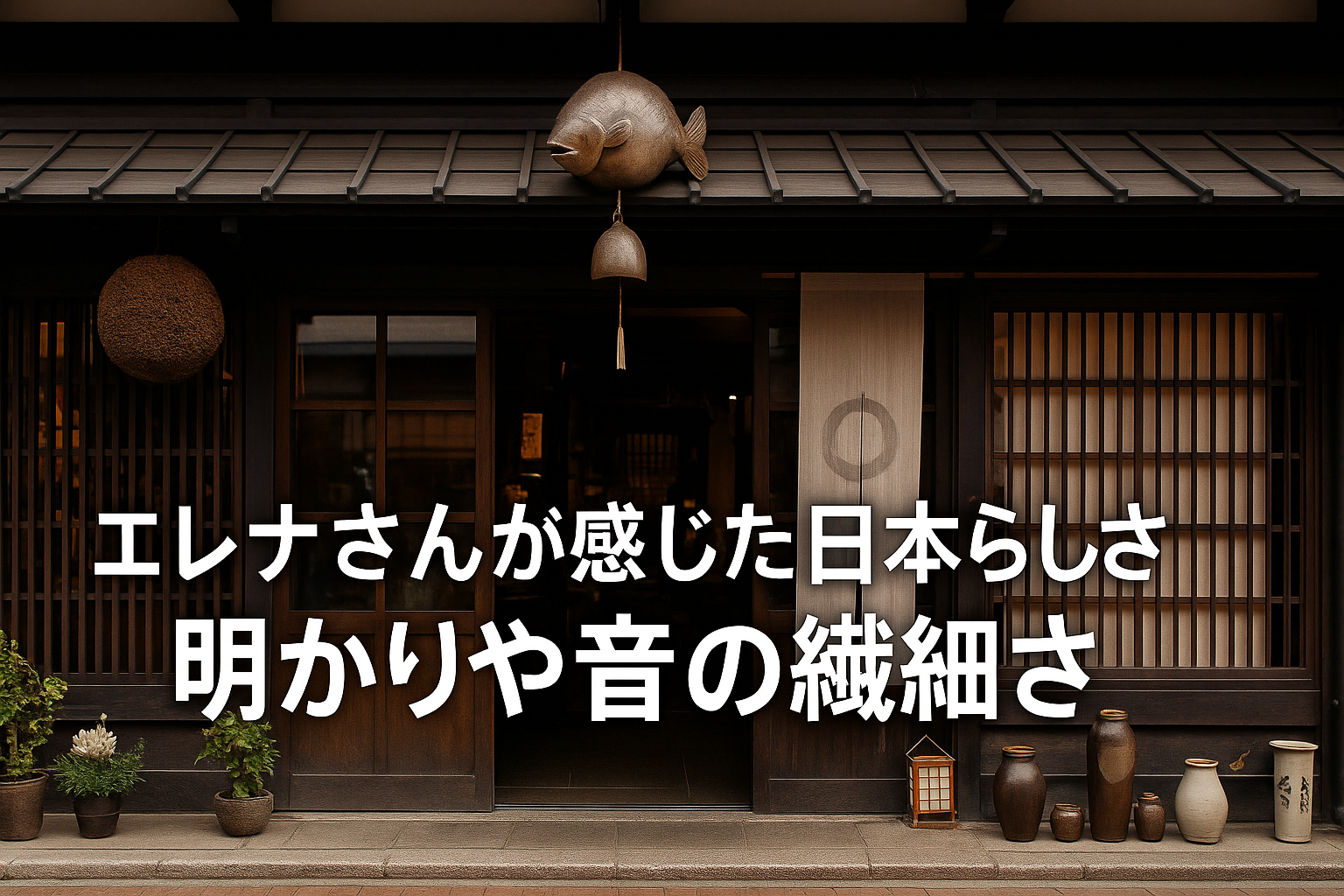

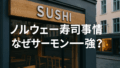
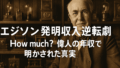
コメント