※本記事はテレビ東京「世界!ニッポン行きたい人応援団」の放送予告をもとに構成しています。放送前の段階で入手できる公式・専門的な情報や信頼できる公開データを整理したものであり、番組で必ずしも同一の手順や数値が紹介されるとは限りません。もし内容が異なる場合は、放送後に改めて確認されることをおすすめします。
銀座の名店「てんぷら近藤」で腕を振るう近藤文夫さんは、天ぷらの世界で最も有名な職人のひとりです。今回の番組では「究極の揚げ方」が披露されるとあって注目が集まっています。しかしテレビ放送では、調理の数値や細かいコツが省略されることが少なくありません。そのため「家庭で再現するにはどうすればいいの?」という疑問を持つ視聴者が多いのでは無いでしょうか。
ここでは、すでに信頼できる情報源に基づいて整理された衣の配合、油温、揚げ時間、素材ごとの下処理と揚げ順などを徹底的に紹介し、家庭での再現に役立てていただける内容をお届けします。
てんぷら近藤揚げ方とは
素材ごとに温度を変える
てんぷら近藤揚げ方の大きな特徴は、素材ごとに油温を調整する点にあります。野菜はおよそ170℃、魚介は180℃を基本とし、複数の素材を同時に揚げる際は油温を少し上げて、野菜なら180℃、魚介なら**190℃**でスタートします。これは油に素材を入れると温度が下がるため、その変化を先回りして調整しているのです。
例えば厚切りのサツマイモ。これは170℃でじっくり揚げるのが基本で、芯まで火が通るまで数分以上かけるのが近藤流です。反対に海老は180℃で短時間。衣がカリッと仕上がる一方で、身はプリッとした食感を残します。
油温を測る温度計がない場合、昔ながらの菜箸テストが有効です。菜箸の先を油に入れて泡が静かに立つのは低温、勢いよく小さな泡が出るのは高温。この感覚を覚えるだけでも家庭での再現性が大きく高まります。
【ごま油の四季】
#ごま油の四季 最新号より東京、銀座駅から徒歩3分!
東京における天ぷらの最高峰
「てんぷら 近藤」をご紹介します✨今回は、店主、近藤文夫さんに
家庭でも作れる天むすを教えてもらいました😆レシピはごま油の四季WEB版に掲載中です💁🏻♀️https://t.co/yBqWXkpFoV pic.twitter.com/AAKiXIxbIq
— マルホン胡麻油[公式] (@maruhon_PR) April 26, 2024
衣の作り方と混ぜ方
近藤文夫さんが強調するのは「衣は空気を食べるもの」という考え方です。重たくベタつく衣ではなく、ふわりと軽やかで、素材の香りを引き立てる衣を目指します。
そのためには薄力粉を必ずふるいにかけること。粉に空気を含ませることで混ぜたときにダマができにくく、軽い仕上がりになります。
卵水は「卵1/2個+冷水200ml」をよく混ぜて作ります。これを薄力粉100〜110gと体積比1:1で合わせます。混ぜるときは3回に分けて軽くサッと。ここでダマを完全に消さず、少し残すくらいが理想。混ぜすぎるとグルテンが出て衣が重たくなってしまうからです。
家庭でのポイントは、材料も卵水もできるだけ冷やしておくこと。温度が高いと小麦粉のグルテンが活発化し、重たい衣になってしまいます。
家庭再現のポイント
家庭用鍋と油の選び方
銀座の本店では銅鍋を使用していますが、家庭なら深めのフライパンや天ぷら鍋で十分再現可能です。油はサラダ油をベースにごま油を少量ブレンドすると香ばしさが増し、家庭でも高級店のような仕上がりになります。
かき揚げを揚げる場合は、フライパンなら油の深さ1〜2cmでOK。材料の下半分が浸かる程度で足ります。揚げ鍋のように大量の油を使う必要はありません。
油量が少ないと温度が下がりやすいので、火加減が重要です。揚げ始めは「強めの中火」、食材を入れた後は「中火」、仕上げは「強めの中火」に戻してカリッと仕上げます。
揚げ時間の目安
食材ごとの揚げ時間は異なります。
- サツマイモ:170℃で3〜4分。厚切りならじっくり芯まで火を通す。
- エビ:180℃で1分前後。プリッと感を残すため短時間。
- レンコン:低温で20分近く揚げる例もある(番組外の専門情報)。泡の大きさと音を見ながらじっくり。
- ナス:100℃前後の蒸気で「蒸すように揚げる」。過加熱に注意。
皆さんどうでしょう?「あなたは普段、揚げ物をするときに時間を計りますか?」。時間だけに頼らず、泡の変化や音のリズムを観察する習慣を持つと、仕上がりが格段に安定しますよ。
世界ニッポン行きたい人応援団・今回の主役は?
放送で取り上げられた背景
今回の放送では、カナダからやってきた天ぷら愛好家が憧れの「てんぷら近藤」で修行する姿が描かれます。近藤文夫さんの直接指導は大きな注目を集め、視聴者はプロの技に驚きと感動を覚えるでしょう。
まとめ
てんぷら近藤揚げ方家庭再現は、放送をきっかけに一気に注目が集まるテーマです。完全にプロの味を再現することは難しいかもしれませんが、数字やコツを押さえるだけでも家庭の天ぷらは大きく変わります。
- 衣は空気を食べるものという言葉を意識する
- 素材ごとに油温を変える
- 泡や音の変化で揚げ上がりを判断する
この3つを実践すれば、家庭でも「近藤流」に近い軽やかな天ぷらを楽しめると思いますよ。
休日に家族と一緒に揚げてみたり、友人との食卓で振る舞ったり。放送を見て気持ちが高まったら、ぜひキッチンで挑戦してみてください。

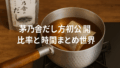
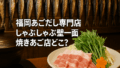
コメント