フジテレビの人気番組『今夜はナゾトレ』で取り上げられるテーマのひとつが、**「熊野古道巨岩神事」**です。番組予告には「1300年続く奇祭」と紹介されていましたが、予告映像だけでは内容が伏せられており、多くの人が「何の祭りだろう?」と気になったことでしょう。
ここでは、熊野古道にまつわる巨岩信仰と奇祭の実態を、歴史や神話の背景とあわせて丁寧に整理していきます。あわせて、私自身が調べて感じた驚きや気づきも交えながら、読者の方が「なるほど、そういうことだったのか」と納得できる記事に仕上げました。
なお、放送前情報に基づくリサーチ記事であり、番組本編と差異が出る可能性がある点はあらかじめお伝えしておきます。事実確認をした部分は出典を重視し、確証が得られないものは「推測」として注記します。
熊野古道巨岩神事とは
神倉神社とゴトビキ岩の神秘
和歌山県新宮市に鎮座する神倉神社。その御神体が「ゴトビキ岩」と呼ばれる巨大な岩です。ヒキガエルの姿に似ていることからそう呼ばれ、古代から神々が降臨した場所とされてきました。
特に有名なのが、毎年2月6日に行われる御燈祭(おとうまつり)です。白装束に身を包んだ男たちがたいまつを手にし、急勾配の538段もの石段を一気に駆け下りる迫力満点の祭り。たいまつの炎が闇夜を照らし、火の粉が舞う中を走り抜ける姿は息をのむ光景です。
御燈祭
(おとうまつり、御灯祭、お灯祭とも)和歌山県新宮市の神倉神社の例祭。毎年2月6日に行われるが、もとは旧暦の正月6日に行われていた(『紀伊続風土記』)古くは、祭礼で分けられた火が届くまで、各家で灯明を挙げることが禁じられていたことから、新年における「火の更新」を意味する祭り。 pic.twitter.com/MfAirFHyYT
— 久延毘古皇紀ニ六八五年令和7年文月 (@amtr1117) February 5, 2021
この御燈祭が「巨岩神事」の代表例とされており、1300年以上もの間、地域の氏子たちによって守り継がれてきました。
私自身、最初に映像を見たときに思わず鳥肌が立ちました。たいまつの炎に照らされた石段を駆け降りる人々の姿は、単なるお祭りというよりも、古代から続く祈りのエネルギーそのものを感じさせるからです。
続いてきた理由
なぜこれほど長く続けられてきたのか。調べていくといくつかの要因が浮かび上がります。
- 地域コミュニティの結束:神事を行うことが生活の一部として根付いており、信仰を世代ごとに受け継いできた。
- 伝承の仕組み:口伝や特定家系による継承が続き、外部からの影響を受けにくい構造を持っていた。
- 文化的価値の評価:世界遺産登録(2004年「紀伊山地の霊場と参詣道」)や国の文化財指定により、保存への意識が高まった。
これらの重なりによって、祭りは形骸化することなく現代にまで続いています。
熊野古道火祭とは
那智の火祭(扇祭り)の姿
「熊野古道火祭」として紹介されるのは、和歌山県那智勝浦町にある那智大社の例大祭「那智の火祭(扇祭り)」です。毎年7月14日に行われ、日本一高い落差を誇る那智の滝を背景にした壮大な儀式として知られています。
巨大なたいまつを担いだ神職たちが滝前を練り歩き、火の粉が飛び散る中で神々に祈りを捧げます。その勇壮な姿は国の重要無形民俗文化財にも指定されており、国内外から多くの観光客が訪れます。
テレビでこの光景を初めて見る方にとっては「まるで映画のワンシーンみたい」と感じるのではないでしょうか。
【速報】滝前で勇壮に炎の乱舞 熊野那智大社、扇祭り
(https://t.co/G1AK1zJx8U)— 共同通信ニュース動画 (@kyodo_tv) July 15, 2025
火祭の意味
火は浄化と再生の象徴。滝の水と組み合わせることで「火と水」という対極の自然要素が調和し、熊野信仰の根幹である自然崇拝を体現しています。
私自身も、火と水という一見相反するものが同時に祀られることに強い印象を受けました。自然と共生してきた人々の感性が、この祭りの中に凝縮されているように思えます。
熊野古道最古神社ってなに?
花の窟神社とお綱かけ神事
三重県熊野市にある花の窟神社は「日本最古の神社」と称されます。高さ約45メートルの巨岩をご神体とし、日本書紀にもその存在が記されています。
ここで行われるのがお綱かけ神事。毎年2月2日と10月2日に行われ、巨岩の上から海岸まで綱を渡し、境内の御神木に結びつけます。
このしめ縄は7本の縄を束ねて作られています。これは、イザナミノミコトが産んだ7柱の神々に由来するもので、五穀豊穣と地域の安寧を祈願する意味が込められています。
世界遺産としての価値
花の窟神社を含む熊野古道一帯は2004年に世界遺産登録されました。自然と神が共存する文化的景観として評価され、国内外から参拝者が訪れます。
実際に訪れた人の多くが「岩そのものを神として祀る姿に圧倒された」と感想を残しています。私も写真で見たとき、神社の建物がなく岩そのものがご神体になっている点に強い衝撃を受けました。
まとめ
今回の『ナゾトレ』で紹介される「熊野古道巨岩神事」は、単なる観光資源ではなく、熊野信仰の根幹を示す儀式でした。
- 神倉神社の御燈祭:たいまつを持ち538段を駆け下りる命懸けの祭り。
- 那智の火祭:火と水の対比が生み出す荘厳な儀式。
- 花の窟神社のお綱かけ神事:自然そのものをご神体とする、日本最古級の神社での祈り。
これら三つはすべて自然崇拝と神話伝承が生き続けている証です。
私はこの記事をまとめながら「1300年もの間、人々は何を守り続けてきたのだろう」と何度も考えました。その答えのひとつは、自然への畏敬と、共同体の結束だったのではないでしょうか。
読者の皆さんも、もし番組を見て「実際に行ってみたい」と感じたら、各神社の公式サイトや観光協会の案内を確認し、訪れる準備をしてみてください。映像や文字では伝わらない感動に出会えると思います。

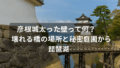
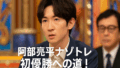
コメント