笠間焼の伝統工芸士になった根本典子さんの歩みが、今じわじわと話題になっています。「人生の楽園」に登場したその姿に、思わず「どうやってそこまで?」と感じた方も多いのでは。
テレビではサラッと紹介されがちですが、根本典子さんが笠間焼で伝統工芸士になるまでには、実はかなりの時間と努力があったんです。放送を見て「私もやってみたい」「どうすればなれるの?」と気になった方もいるのでは。この記事では、そんな疑問にお応えすべく、資格取得の流れや必要な経験、そして根本さんならではのルートを、あたたかく掘り下げてみました。
笠間焼ってどんな焼き物?
素朴であたたかい器の魅力
茨城県笠間市を拠点に作られる笠間焼。江戸時代から続く歴史がありながら、自由でのびのびした作風が特徴です。手に取ると、どこかホッとするような温もりがあって、日常使いの器として根強い人気を誇ります。
【潜入!茨城県の伝統工芸品展】
県人会事務局です
6/19まで伝統工芸青山スクエア(港区赤坂8-1-22)で開催されている#茨城県 の伝統工芸品展に行ってきました!おしゃれな笠間焼
かっこいい真壁石燈籠
きれいな結城紬それぞれを一度に堪能できました
詳細については今後お伝えしていきます🫡 pic.twitter.com/2xGuXSGOVo— 茨城県人会連合会 (@Kenjin_Ibaraki) June 10, 2025
他の焼き物との違いは?
たとえば益子焼や信楽焼といった他の有名焼き物と比べても、笠間焼は“型にとらわれない個性”が魅力。作家ごとに雰囲気が違うのも楽しいポイントで、最近は猫モチーフなど、若い世代の心をつかむ作品も続々登場しています。
伝統工芸士って、どうすればなれるの?
実務経験が何よりの土台
一番大事なのは、「経験」。笠間焼の製作に12年以上関わり、今も続けていることが条件なんです。つまり、“長くじっくり続けること”が何よりの近道というわけですね。
試験のステップ、ちょっと覗いてみると
書類審査のあとには、実技試験・知識試験・面接試験が用意されています。実技では手びねりやろくろなどの腕前、知識試験では素材や歴史についての理解が見られます。しかも合格して終わりじゃないんです。5年ごとの更新審査があるため、ずっと技術を磨き続ける姿勢が求められます。
根本典子さんの歩みをもう少しだけ深掘り
シングルマザーという背景と陶芸の出会い
シングルマザーとして、毎日を必死に生きていた根本典子さん。そんな忙しい日々の中で出会ったのが陶芸でした。焼き物の温かさに心がほぐれ、「もっと知りたい、作ってみたい」と思うようになったそうです。
そして2025年、伝統工芸士に認定
12年以上積み上げた努力が実を結び、2025年2月に念願の伝統工芸士に認定。茨城県内で23人目、女性としてはなんと2人目の快挙!これって本当にすごいことなんです。番組では“難関試験に合格”とサラッと触れられていた部分にも、実は数えきれないほどの努力があったんですね。
同じ道を目指すなら、何から始める?
学ぶ場所、ちゃんとあります
「陶芸ってどこで学ぶの?」と思った方、ご安心を。笠間市には「笠間陶芸大学校」があり、基礎からしっかり学べる体制が整っています。2年制の学科と1年制の研究課程があり、ここでの経験も実務年数にカウントされるんです。
技術だけじゃなくて発信も大切
今の陶芸家には、“つくる力”だけでなく、“伝える力”も求められています。根本典子さんも、SNSで自作の器やネコの作品を発信していて、ファンとの交流も楽しそう。ちなみに最近、某有名女優さんが陶芸にハマっているという話も。やっぱりこの世界、静かにブーム来てます。
笠間焼が人気を集める理由って?
- 日々の食卓になじむ使いやすいデザイン
- 一点モノのような個性が光る作品たち
- SNSでも映える、美しい色合いや形
ちょっとしたギフトにもぴったりで、ひとつ食卓に置くだけで空気感が変わる。そんな魅力が詰まっています。
実生活でどう使う?3つのアイデア
- お気に入りのマグカップにして、朝を気分よくスタート
- 来客時のおもてなし用に、小鉢や豆皿として
- 玄関やリビングに置いて、ちょっとした花器や小物入れに
日々の暮らしの中で、ちょっとだけ「好き」を取り入れる。そんな使い方が似合うのも笠間焼の良さですね。
【まとめ】
笠間焼の伝統工芸士になるには、長い経験と技術に加えて、地域とのつながりや継続的な成長が必要です。根本典子さんのように、子育てや仕事と並行して夢を追い続けた姿からは、大きな勇気をもらえます。テレビでは触れられなかった「その先のストーリー」を、この記事で補うことができたなら嬉しいです。「焼き物の世界、ちょっと面白そう」と感じた方は、ぜひ一歩踏み出してみてくださいね。
※本記事は放送前情報をもとに執筆しており、番組内容と一部異なる可能性があります。


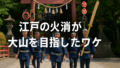
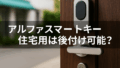
コメント