13歳で家を飛び出し、43年間も洞窟で暮らしていた男性が実在した――そんな信じがたい話が、フジテレビ『世界の何だコレ!?ミステリーSP』で取り上げられ、注目を集めています(※放送前情報に基づく記事です)。
番組で紹介されたのは、加村一馬さん。1946年、群馬県大間々町に生まれ、13歳で家出して足尾銅山周辺の洞窟にこもり、実に洞窟生活43年を送った実在の人物です。背景には家庭内虐待や学校での孤立という過酷な事情がありました。彼の生活は「洞窟おじさん」として一部では知られており、その生き様は、現代社会に生きる私たちに多くの問いを投げかけています。
洞窟生活43年
洞窟生活の始まりと背景にあったもの
加村一馬さんが13歳で家出した理由は、家庭内の暴力と学校での孤立でした。特に父親からの虐待は凄まじく、夜中に墓石に縛られるといった体験も。逃げ場のなかった少年時代、愛犬シロとともに山を越えて足尾銅山の洞窟へ向かいます。自然と一体になったサバイバル生活はこうして始まったのです。
足尾線廃線跡
足尾銅山
古川橋 pic.twitter.com/YwR5CrRUut— でぃーほん (@jfmamjjasond_) July 27, 2025
食料や道具はどう確保していたのか?
干し芋に始まり、川魚、山菜、カタツムリ、マムシの血と、想像を絶する食生活が続きます。火の管理も命に直結する技術で、ツルで編んだ扉や、落ち葉と枝を使った寝床など、自然との共生を体現した日々。彼の生活は、まさに“生き延びること”そのものでした。
最近読んだ本でぶっちぎりで面白かったのは、43年間サバイバル生活をしていた『洞窟オジさん』です。人間の毛髪で蛇を捕獲する方法とか、ウサギの皮で靴をつくったり、ヨモギを止血に使ったりなどの衝撃的なライフハック(?)が勉強になります。 https://t.co/mUbHVog3Uu pic.twitter.com/gTxZvfMmKQ
— 平川哲生 Tetsuo Hirakawa (@bokuen) March 18, 2023
加村一馬
実在する「洞窟おじさん」とは何者なのか
加村一馬さんは1946年生まれ。57歳で発見場所が判明するまでの洞窟生活43年をひたすら一人で生き抜きました。その姿はNHKドラマや書籍『洞窟オジさん』でも描かれていますが、今回の再注目で若い世代にも知られる存在となっています。
『洞窟オジさん』
人生の殆どを洞窟で過ごした人の実話
13歳の頃に愛犬のシロを連れて両親の虐待から逃げ、57歳で見つかった著者はなぜ障害者支援施設で働くことになったのか?
山から人間社会に戻ってからの苦悩も描かれている
貴重で衝撃的な体験談が気になる方にhttps://t.co/7U92g0NXZ4
— おすすめ聴き放題ノンフィクション@30日無料で聴き放題(bot) (@nonfiction397) June 30, 2025
発見当時の状況とその後の暮らし
発見されたとき、加村一馬さんは言葉も明瞭で、何より「人に迷惑をかけたくない」という哲学が印象的でした。現在は群馬県桐生市の障害者支援施設で穏やかな生活を送り、かつての極限状態とは対照的な日常を築いています。
群馬 家出少年の壮絶サバイバル体験
家出から始まった想像を超える暮らし
家出後、足尾銅山の洞窟を起点に、新潟・福島・山梨といった山奥を転々と。廃屋や橋の下で寝泊まりしながら、社会から距離を置いた生活を送りました。移動は徒歩、人目を避け、静かに生きる彼の姿に、都市生活では得られない本当の自由があったのかもしれません。
長期サバイバルを支えた信念と孤独
「誰にも頼らずに生きる」という覚悟、それが加村一馬さんの核でした。愛犬シロとの日々や、偶然出会った夫婦からもらった白米と味噌汁に感動した体験など、人との接点が人生を変える瞬間もありました。孤独と向き合う姿勢が、多くの人の共感を呼んでいます。
鉢アブ退治できる人
ムカデつぶせる人
蛇に出会っても素通りできる人
カナブン顔に直撃しても大丈夫な人
自販機からジュースより先に
カメムシ出てきても大丈夫な人
クーラーなくても大丈夫な人
牛乳一本買いに行くのに8000歩歩ける人私を守ってください🤣
サバイバル生活です
⇨🛌🤦♀️ pic.twitter.com/0TXJUJe0Ee— Miyabi Mori (@miyabipf) August 1, 2021
【関連する人物や社会的文脈】
実は以前『激レアさんを連れてきた』でも加村一馬さんの話題が取り上げられており、メディア再登場の文脈でも注目度が上がっています。
【まとめ】
加村一馬さんの洞窟生活43年は、単なるサバイバルの記録ではなく、「人がどう生きるか」の問いそのもの。虐待や孤立、そして逃避という背景がありながら、社会に戻る道を選んだ彼の姿には、多くの気づきがあります。
今、注目を集めているのは、私たちが日々感じるストレスや都市生活への違和感から、「別の生き方がある」ことへの憧れと、ここまで人は生きられるのかという驚きが重なっているからです。彼の物語には、時代や場所を越えて響く何かがあると、私は思います。
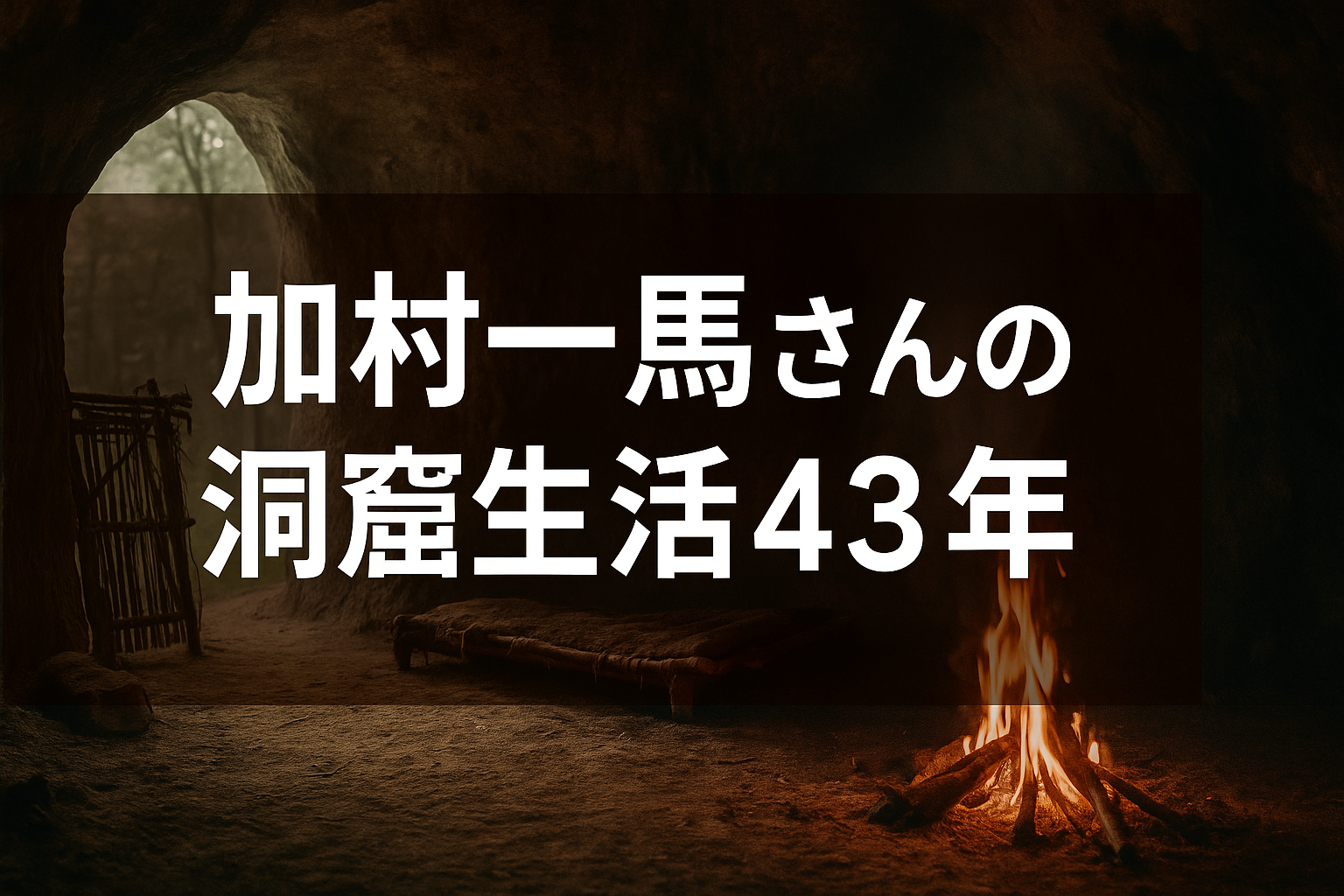

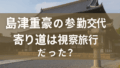
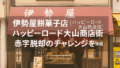
コメント